ポルソナーレのサイト内検索
全日本カウンセラー協会・ポルソナーレのマスターカウンセリング
読むだけで幸せになる手紙
子どもの脳は破壊されない、と父親から教えてもらった私日本人の心と精神の病は、分裂病か鬱病といわれています。 |
|---|
わたしは、地方の公務員です。高校を卒業してすぐに公務員になりました。6年目です。 わたしは、明るいと暗いのが交互にあらわれる性格です。 明るいときは、上司にもふつうに話せます。そういうときのわたしは、魅力に輝いて見違えます。 暗くなると誰と話す気力もなくなります。辛くて、舌がもつれます。顔もひきつります。声が別人のように老けて、しわがれて、うめき声がしぼり出るように発語されるのです。 高校を卒業するころ、このままでは仕事にも行けないと思い、精神科に行きました。医者は、躁と欝の両方がくりかえされていると言いました。 躁のときは、気が大きくなり、自信満々になります。まわりも明るく、活気にあふれます。 こういうときは、自分が頼もしくて、嬉しくなります。 なんだ、仕事も人間関係も簡単じゃないか!! こういう日は三日しか続きません。 わたしの父親は、気がついた時には精神分裂病でした。学校の教師だったので、辞めさせることはなかったようです。 父親の病気の症状は、暴力をふるうとか暴言を吐くということはありませんでした。性格はおだやかでおとなしく、いつもにこにこしていました。 時々、長い間入院しては帰宅してきました。どこか南の島へレジャーで遊びに行って、リフレッシュして戻って来たようです。 「ただいま」と言います。 「いい子にしてた?はい、おみやげだよ」。 いつも小さなクマのぬいぐるみがおみやけです。 小さなクマは「こんにちは」とかわいい声で言ってくれます。 「こんにちは」 わたしもにっこり笑顔でごあいさつをします。 父親が退院して帰宅する日は、いつもきまって夜です。 空にはまるい月が赤く輝いていました。あずき色とも赤とも、黒ともいえないような色の月がありました。 父親は、調子がおもわしくないときは、ひとりでブツブツと話しています。頭の中にある誰か、ひょっとして何かに怒っているということがよく分かります。不機嫌で、うつむいて、手の指はこまかく動いて何かの作業をしているふうです。 わたしは、そんな父親がとても恐かったのです。 キライと思って反発心もおこります。恐いと思うときは、体が震えるくらいびくびくして息が詰まりました。 母親の精神状態も、父親の影響をうけて、ひどく不安定でした。 躁と欝のバイオリズムは3日か4日おきだったのが、1週間おきになりました。 欝のときは、沈黙がこわいのです。いったん沈黙すると、この沈黙のカベを自分で破る勇気がなくなります。 もうひとりの自分がふわりと空中に浮いていて、一歩も動けない自分を冷たく見ています。 なぜ?どういう理由で?動く理由をいっしょうけんめいに探しつづけて一歩も動けない自分がいます。ひとりだけ別世界に閉じこもっているのです。 人の目を意識して、ひどく視野が狭くなった中に寒さに震えながら泣きたくなるのをこらえている自分が見えます。 「こわいよー、寒いよー、誰か暖かくしてよー」。 |
 谷川うさ子さん |
ポルソナーレのカウンセリングです。 ハンナ・アーレントの『人間の条件』(ちくま学芸文庫、ポルソナーレの特設ゼミの『谷川うさ子哲学入門』のテクストをご参照ください)とか、吉本隆明さんの「個体・家族・共同性としての人間」(『情況への発言』徳間書店)の哲学を勉強した人にはよく理解できることですが、人間の脳には、強固で強力な共同体、共生の記憶がつくられています。 現実のものごとのどんなことも、哲学の知性を判断の基準にすると、真か偽(ぎ)か?の区別がつきます。 0歳8ヵ月までに完成される乳・幼児の脳の中の驚異の共同体、共生の記憶が壊れないかぎり、人間は、つねに正常な知性や精神、心を志向して生きようとします。 ご紹介した物語の赤井月三田子さん(仮名・25歳)は、父親が精神分裂病でも、社会的な行動力は身につけています。脳の中の共同体、共生のメカニズムの効果であるとは、誰も気づかないでしょう。女性の脳の働きのしくみの認識力が行動する力を手に入れています。 不足しているのは、日本語のもつ言葉の曖昧さを正しく共同体、共生に見合わせることです。 女性なら誰でも、洋服を買うとき、自分の体のサイズに合わせますね。 そんなふうに合わせると躁も欝も正しく回復の道をたどるのです。 わたしは、ポルソナーレから、人間関係に自信がつくアドバイスをいただきました。 それは、「人は人」「言葉は言葉」という分け方をする、ということです。 家に帰って、父親の話を聞いてみました。 「人が自分をどう思っているのか分からない」と言います。 わたしは父親の言葉を自分にむすびつけていました。 「人が」は、「わたし、赤井月三田子が」と短絡させていたことに気づきました。 わたしは、父親がひとり言を言っていたので、自分から話しかけてもいいのやら、どうなのやら、と分からなかっただけなのです。 「わたし、お父さんのこといつも心配していました」と言いました。 「そうだったんですよ」 母親も言いました。 「そうだったのか!」 父親は、わたしと母親の気持ちの輪の中に入って、温泉に肩まで浸かったような晴々とした表情になりました。 その日は、夜の空の月はレモン色に輝いて、しゃぼん玉のように浮んでいました。 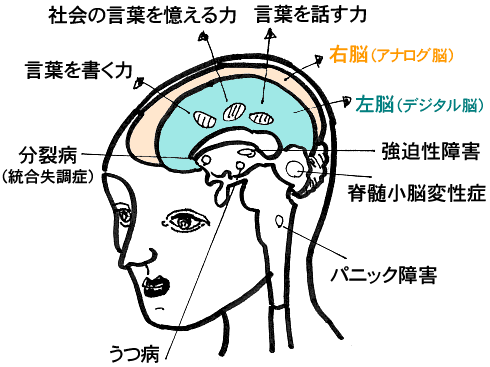 |
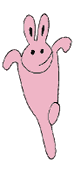 谷川うさ子さん |
←前へ 次へ→






























