| (1) |
人は、困難な問題に直面した時、「自分にはとても乗り越えられない」と思ってしまうことがある。10数年前にも出会ったある若い母親がそうだった。 「自分には、とても乗り越えられない」と思った。
この若い母親は、結婚して初めて出産を迎えた。男の子が生まれた。生まれた男の子は重度の障害を持っていた。
「二分脊椎(にぶんせきつい)」という障害だった。医者は告げた。
「手術をすれば二十四カ月生きた例があります」。 |
| ●先天性障害「二分脊椎」 |
| |
「二分脊椎(にぶんせきつい)」とは、「脊椎」の中を通る神経管に発生異常があって、脊椎から腫瘤状になってとび出している先天性の障害のことだ。「水頭症」を併発することが多い。
現在では、早期の治療によって「長期生存」が可能になる例が多くなっている。だが10年前の当時は確かに「予後」が厳しい例が多かった。
「手術すれば、二十四カ月生きた例があります」という医師は少しでも親を慰めようという思いで言ったと思われる。
「厳しい障害なので一年以上生きるのは難しい。手術などで手を尽くした結果、二年生きたという学会での報告もあります」。「二年生存」を成果とする医師の観点だ。
母親は22歳だった。治療の手を尽くしても二年しか生きられないのか、と思った。
絶望した。「この子と一緒に死のう」と思いつめた。
どんなにがんばっても最大で二年間しか生きられないのか。そんな残酷な先が分かっているのにどうやって、明日からこの子に接していけばいいのか?どうやってこの子に笑顔をつくればいいのか。自分は何を支えに生きていけばいいのか。母親は「生きる支えになる言葉」を求めたのだ。それがないから「母子心中」まで考えた。彼女には母親がいた。
この母親が娘の表情を見て何ごとかを察知した。
「死ぬのはやめなさい。この子がかわいいじゃろう」。
このひと言で若い母親は、死を思いとどまった。
「この子をなんとしても生かしてやりたい」と思い直した。思いつくかぎりの病院や施設を訪ねた。そして可能なかぎりの治療と、療育を受けさせた。男の子は、見事に生き抜いた。男の子は成人した。今、車椅子で仕事に就いている。 |
| (2) |
一九八二年。
江口敬一は、アメリカ西海岸にある「YKK、U・S・A社」のシアトル支社に勤務していた(住宅建材、ファスナーなどの大手メーカー)。
この年の九月。シアトル市内の病院で次男、裕介が生まれた。
長男の俊介君は、シアトル勤務前のロサンゼルス時代に生まれている。元気に育っていた。
江口夫妻は、次男が無事に生まれたことを心から喜んだ。
しばらくたったある日。医師が夫妻に赤ちゃんの診断の結果を伝える。
「残念ながら次男の裕介君は、染色体検査の結果、ダウン症候群であることが分かりました。知的障害もあるのです」。 |
| ●「ダウン症候群」という障害 |
| |
江口夫妻はショックを受けた。すぐには言葉も出ない。医師はさらにこう話をつづけた。
「あなた方は、障害をもった子どもを立派に育てられる資格と力のあることを神様が知っておられてお選びになったご夫婦です。どうぞ、愛情深く育ててあげてください」
江口夫妻は、この言葉で我にかえった。
「この子を自分たちが育てなくては、誰が育てられようか。この子の親として選ばれたからには、愛情をこめて育てなければならない。医師が言ってくれたように自分たちには力があるはずだ。可愛い子のためならできないことはない」。
江口夫妻は、医師の言葉によって勇気づけられた。
医師は、医学的な診断結果の説明をしただけで「会話」を終わりにしなかった。倒れそうな夫妻の心を支えた。江口夫妻は思い直すことができたのだ。 |
| ●「療育」が必要 |
| (3) |
医師はさらに話した。
「ダウン症児」には「筋肉の発達」と「知的発達」をともに促進するために「早期療育」が必要であると話した。
「早期療育」にはそのシステムのあるシアトルのワシントン大学がいいと紹介してくれた。日本の小児科医や産婦人科医の中にもこのアメリカの医師の患者の親への対応を当然のこととして実践している医師がかなりいる。
岡山県の「重度心身障害児」の施設、旭川荘理事長の江草安彦医師の話。
「私たちの仲間は、みんな、そういう言葉がけをするのを日常の心掛けにしているのです」。
だが、医療界全体を見ると、患者、家族の心情を配慮したコミュニケーションはきわめて未成熟なのが日本の国の現実なのだ。だいいち医学教育のカリキュラムの中にそういうコミュニケーションの「教育」「研修」の場が設定されていないのである。 |
●親を教育する |
| (4) |
江口夫妻は、「ダウン症」の裕介君をワシントン大学の「ダウン症児早期療育」のプログラムに参加させた。「赤ちゃん体操」のようなことから始められた。「筋肉」と「知能」の発達を促すために全身に刺激を与えるというのが目的だ。
江口氏が感動したのは「教育プログラム」が「ダウン症児」だけを対象にするのではなくて、同時進行で「親」に対する「障害」をもつ子どもへの「接し方」や「親としてのあり方」にかんする「セミナー」を設けていることだった。
江口氏は「父親」にたいする「ファーザーズ、プログラム」を受講した。
「父親が障害について正しく理解することの重要性」「家族における子どもの育て方と父親の役割」など、実践実技にむすびつく学びが多かった。 |
| ●「父親の出番がやってくる」 |
| (5) |
江口敬一は、「障害をもった裕介をしっかりと育てる、少しでも自立できる道をつけさせる」と考えた。「父親として仕事をなげうってでも裕介のために全力を尽くしてやりたい」「海外の勤務は責任が重い。仕事も大変だ。このままでは会社の仕事は無理かもしれない」。
「ファーザーズ・プログラム」が進む中でセラピストの一人に相談した。
「ミスター・エグチ。誰でも障害をもった子どもが生まれると気持ちがその子どもだけに集中します。距離をとって考えられなくなる。今すぐに子どものために何かできることはないか?と考えます。なかには、会社や仕事を辞めてしまう父親もいます。
けれども、それではいい答えを出すことにはならない場合が多いようです。
あなたが父親としての役割を果たす時、父親の出番というものが、いずれ、必ずやってくるのです。そまで待っていましょう。焦らないことです。どうぞ、性急に考えないでいただきたいのです」。
このセラピストの言葉は、江口敬一の胸にまっすぐ入ってきた。「父親の役割」「父親の出番」という言葉が心の中に灯をともした。あったかく懐かしく、オレンジ色に輝いていた。 |
| ●「療育の考え方をもってください」 |
| (6) |
江口敬一は、YKKの勤務をつづけることにした。
「ダウン症児の裕介君」が「早期療育プログラム」を受けて、半年が過ぎた。江口敬一は考えた。
「アメリカの医療、福祉の取り組みはすばらしい。だが、裕介が青年になる頃、アメリカと日本のどちらが社会になじみやすく、また生きやすいのか?」。
江口敬一は、、再びセラピストに相談した。
「二つの理由から日本に帰ったほうがよいと思えます。一つは、知的障害のある人がバイリンガルで生活するのは困難です。もう一つは、父親と母親だけで子育てをすると荷が重くなる時があります。どうしても祖父母、周りの人のサポートが必要になります。何ができないか?ではなく、何ができるか?をつねに考えられる父親、母親でありつづけることを、どうぞ、お考えになってください」。 |
| ●「療育」の考え方 |
| (7) |
一九八九年八月。
裕介君はもうすぐ一歳になろうとしていた。江口敬一の転勤願いが認められた。江口敬一は、家族ともども日本に帰国した。勤務先はYKKの大阪支店だった。住居は、もともと住んでいた東大阪市だった。
江口敬一は、「ダウン症児の裕介君」を日本で育てるにあたり、妻と「育方針」を話し合った。「考え方」にズレがないようにするためだった。
「他人の痛みが分かる、思いやりのある人に育つようにしよう」
「できないことは、自分の意思で他者にサポートを頼み普通に生きられる人にしましょうね。そのためには家族も結束して、サポートが必要なことについては親としてできることは何でもしてあげましょうよ」。 |
| ●小学校」「中学校」そして「高校」へ |
| (8) |
江口夫妻は、「ダウン症児の裕介君」を普通の子と同じように育てようと考えた。親戚でも近所でもオープンに連れていく。近所の子どもたちとはできるだけ一緒に遊ばせた。「小学校」「中学校」は地域の一般の子どもたちと同じ学校に通わせた。「高校」は「養護学校高等部」に通わせた。裕介君は、「高等部三年」になった。「職場実習」を経験した。「僕は働きたいよ」と言った。 |
| ●「働く」 |
| (9) |
二○○一年三月。
「ダウン症の裕介君」は、「養護学校高等部」を卒業した。東大阪市内の「高齢者ディ・サービス・センター」の「アンデスのトマト」に就職する。
職種は「作業補助」だった。利用者にお茶とお菓子を出すこと、フロント、トイレの掃除、洗車、昼食の配膳、レクリェーションの手伝いだ。一週間の事前実習で「就業可能」と認められて「採用」と決まったのだ。 |
| (10) |
二年が経った。江口敬一は、「大阪市職業指導センター」で「知的障害のある人のためのホームヘルパー3級の養成講座」が開講されるということを知った。
裕介君の仕事がマンネリになってきていた頃だった。
江口敬一は、裕介君に講座の内容を説明した。裕介君は説明を聞いた。
「勉強したいか?」と尋ねる。
「勉強したいよ、お父さん。教えてくれてありがとう」。
裕介君はにこっと笑顔で答える。 |
| ●「ホーム・ヘルパー3級」の資格 |
| (11) |
「ダウン症児の裕介君」は、二○○三年五月から七月までの二ヵ月間の講習を受けた。「ホーム・ヘルパー3級」の資格を取得した。
だが、「ホーム・ヘルパー3級」では利用者の身体に触れる業務に携わることはできない。だから、ディサービス・センターではまだ「補助作業」の仕事しかできない。職員となって正規の介護業務に携わるには「ホーム・ヘルパー2級」の資格が必要だった。「ダウン症児の裕介君」は「ホーム・ヘルパー2級」の「養成講座」に挑戦しようと考える。「お父さん、やってみるよ。応援してくれてありがとう」。裕介君はにっこり笑顔で言った。
二○○四年一月。新しい年が明けたさわやかなある日のことだった。 |
| ●ホーム・ヘルパー2級」の養成講座 |
| (12) |
二○○四年一月から三月にかけて開講された「ホーム・ヘルパー2級の養成講座」。「ダウン症児の裕介君」は講座に通いはじめる。テキストは「講義編」だけでも厚さが「一○五センチ」もある。けれども文字は大きい。分かりやすい言葉で書いてある。イラストも入っている。「障害者」についての説明の章には「ダウン症の人とは」と講義されていた。
「なんだ、ぼくのことやないか」と初めて「ダウン症」について知る。
「お父さん、お母さん。ぼくはひょっとして障害があるかもしれへんよ。今まで気がつかなかったけどね」。
「ダウン症の障害をもっている人のためにもがんばってみたいんよ」。
裕介君の目には力がこもっていた。庭には水仙の花が素敵な香りをただよわせているある日の昼下がりのことだった。 |
| ●実技編の「実習」 |
| (13) |
「ホーム・ヘルパー2級の養成講座」は「実技編」に入った。また、新しいテキストが渡される。「排泄・尿失禁の介護」の章がある。「実習です」と「紙おむつを着けて寝てみましょう」という課題が与えられた。
その日の夜。
「お母さん、サポート、サポート」と裕介君が呼ぶ。江口夫妻は、裕介君の部屋に行く。「ダウン症の裕介君」はベッドの上に仁王立ちになっている。必死に紙おむつをつけようとしている。「紙おむつ」は赤ちゃん用で小さい。
なかなかうまくつけられない。
「うわーっはっはっはっはっ、わーっはっはっはっ、うわーつはっはっは」と父親と母親は爆笑した。
裕介君も爆笑する。
「あーっはっはっは、わーっはっはっは!」。
母親がてつだってなんとか「紙おむつ」をつける。「ダウン症の裕介君」は、その夜、「紙おむつ」をつけたままで寝た。辛い心身者の気持ちに思いを寄せた。
窓からはまるい月が銀色の光が入ってくる。「ダウン症の裕介君」の顔を照らしてキラキラと輝いていた。 |
| ●道標を無底の奈落にうがつ |
| (14) |
「ダウン症の裕介君」は「ホーム・ヘルパー2級」の講座の講義の復習をがんばった。予習もやる。文章を声に出して読む。これがよかった。「養成講座」は7人の受講生がいた。「ダウン症の裕介君」は、この7人の受講生と一緒に「ホーム・ヘルパー2級」の資格を取得した。それはもう画期的といってもいい出来事だった。「ダウン症の人」が「ホーム・ヘルパー2級」の資格を取得したのは、大阪では初めてのことだった。それは、「知的障害」をもった全ての人の「自立」「社会参加」「単独で生きる」ということへの「一里塚」という道標を無底の奈落の底にうがつものといってもよいものだったのだ。
庭では、ピンクのチューリップがウサギの耳のように春風を受けてゆらゆらと揺れていた。 |
| (15) |
話は、一九九五年にさかのぼる。「ダウン症の裕介君」が「中学生」になった四月の頃のことだ。
江口敬一は、ある新聞の記事を目にする。
「ある電力会社が、障害のある人たちが働くための特別子会社を立ち上げた」。
「特別子会社制度」とは、「障害者雇用促進法」にもとづく会社のことだ。
「一定度以上の従業員を雇用している民間企業は、従業員の一・八パーセント以上の障害者を雇用する義務を負う」。
「しかし、業務内容から障害者の雇用が困難な場合は、事業主が、障害者を多く雇う子会社を設立すれば親会社が雇用したのと同じとみなす」。
この特例でつくられた子会社が「特別子会社」だ。 |
| ●「特別子会社」の設立趣意書 |
| |
江口敬一は、夫人と相談した。「特別子会社では障害者はどのような仕事の場を得ているのだろうか?」。
江口夫妻は電力会社の「特別子会社」を訪ねた。会社の責任者が応待してくれた。仕事の現場を見せてくれた。「特別子会社」の設立の意義を話してくれた。設立の手続きと留意すべき点を教えてくれた。
「ご子息の将来のことも大切です。だから、YKKさんでも特別子会社をつくって、障害のある人をもっと雇用してあげてくれませんか」。
江口敬一は、胸を衝かれた。
「自分は、息子の将来の就職のことばかりを考えていた。働くことで社会参加をしようと望んでいる多くの障害者たちのことを視野に入れて考えるべきではなかったか」。
江口敬一は、どのような業務の「特別子会社」がつくれるかのリサーチにとりくんだ。
4カ月かかって「特別子会社」の「業務の内容案」を盛り込んだ「設立趣意書」をまとめた。
「事業内容は、YKKが製造販売しているアルミサッシなどの住宅建材、ファスナーなどの数々の賞品のカタログと取扱い書の印刷を請け負う印刷会社をつくろう」 |
| ●YKKグループの吉田忠裕社長 |
| (16) |
一九九五年の九月。
YKKグループ本社から吉田忠裕社長が大阪支店に視察に来た。
江口敬一は、大阪支店長と一緒に昼休みの時間帯に吉田社長に会った。「特別子会社の設立案」を直接、説明する機会を得た。
異例の上申だった。
吉田社長は説明を聞く。しばらく沈黙して考える。そして言った。
「趣旨に賛成します。資本金として二億円出します。君に五年間の猶予期間を与えましょう。五年目で単年度黒字を出せる事業計画を出してください」。
障害者を雇用する「特別子会社の設立」のために、二億円も出すというのだ。
吉田社長は絶大なエールを送った。江口敬一の目の前がパッと明るくなった。
窓の外では、秋空が青く、どこまでも高く広がっていた。
|
| ●障害者だけを雇用 |
| (17) |
一九九九年、四月一日。
「特別子会社YKK六甲」が、神戸市の六甲アイランドにある広大なYKK尻手場敷地の一角に立てられた「平屋建ての専用工場」で操業を開始した。
社長には江口敬一が就任した。
従業員は、「聴覚障害者」「下肢または上肢障害者」「知的障害者」が合わせて10人、「パソコン」と「印刷機の技術指導者」など5人、計15人だった。
おもな従業員は、「印刷物のレイアウトなどをつくるパソコンルーム」と「印刷機が回転する部屋」、「印刷物を荷造りする出荷準備室」といったところだった。
障害者の中には「阪神・淡路大震災」でタンスの下敷きになり、「下半身麻痺」の「肢体不自由者」になった青年もいた。 |
| ●2年めで単年黒字化 |
| (18) |
二○○四年十二月
「特別子会社YKK六甲」は、設立から五年が経った。
「障害者」は14人に増えた。誰もが黙々とパソコンに向かって仕事をしている。誰もが表情は清々しい。
江口敬一社長は話す。
「従業員は、誰も、就業して一年もするとパソコンでカタログや取扱い説明書などを作成する仕事をどんどんこなせるようになります。超ベテランになった一人は、障害はあるけれども、作業の流れをIT化で管理するシステムまで作りました」。
「働く場を得て、しかも、今までできなかったことができるようになると、二人で一人前ではなく、一人で一人前の仕事がこなせるようになります。社会的な自立感をもてるようになります。この二つが障害を持っている人たちにとって、心の底からの大いなる生きる喜びになるのですね。自暴自棄になっていた若者は、働く場があると、人間として人が変わるのです。自立感をもたらす幸せの結晶が恋愛です。ここで働く聴覚障害者どおしのカップルが一組、生まれました。彼らは、未来を見つめて心を生かし合うために結婚しました」。
「特別子会社YKK六甲」は、二年目に単年「経常黒字」になった。
五年目には、「営業収支」が黒字になった。
六甲の水はおいしい。だから空気がきれいだ。六甲の山並に沈む夕日はいつだって大きくオレンジ色に輝いてゆっくりと沈んでいく。 |
| (19) |
「ホーム・ヘルパー2級」の資格を取得した「ダウン症の江口裕介君」は毎日、「アンデスのトマト」に出勤している。給与のことはまるで無頓着で心から嬉しそうに帰宅する日々がつづいている。障害者の人のために役に立っていることが生きる喜びを湧き上がらせる。
「裕介のための父親の出番と思って設立した特別子会社は、さしあたり役に立ちませんでした。でも、より多くの障害者たちに働く場を提供する14年目の男の出番にはなりました」
さらに江口敬一は語る。
「心身にトラブルをもつ子どもをもつお父さんたちが、仕事とわが子への愛情を両立させる意味でも、こういう子会社をつくる道を探してほしいと願っています。私がYKK六甲で実現させたことが、そういう人たちの励ましと勇気づけになればこんなに嬉しいことはありません」。
江口敬一
昭和二十四年生(一九四九年)に生まれた。五十五歳。次男「ダウン症の子ども」の社会的な自立を考えつづけてきた。神戸市東灘区にある「YKK六甲株式会社」の社長を務めるに至っている。 |
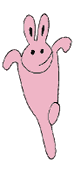
 ケーススタディー
ケーススタディー ポルソナーレ式セカンドステップ
ポルソナーレ式セカンドステップ ハーバード流交渉術
ハーバード流交渉術 『14年目にやってきた男の出番』
『14年目にやってきた男の出番』 『免疫革命』(安保徹・講談社インターナショナル)
『免疫革命』(安保徹・講談社インターナショナル) 『治療薬マニュアル』(2003・医学書院)
『治療薬マニュアル』(2003・医学書院) 『脳、100の新知識、その形態から疾患まで』
『脳、100の新知識、その形態から疾患まで』 『ハーバード流交渉術』
『ハーバード流交渉術』
 「女性向け」、「男性の“女性”対応」のカウンセリング・ゼミです。
「女性向け」、「男性の“女性”対応」のカウンセリング・ゼミです。 女性と心を分かち合える「脳」を、最高に発達させる!!が教育の狙いと目的です。女性を「見る」「見たい」、女性から「見られる」「見られたい」関係をつくる、カウンセリング術です。
女性と心を分かち合える「脳」を、最高に発達させる!!が教育の狙いと目的です。女性を「見る」「見たい」、女性から「見られる」「見られたい」関係をつくる、カウンセリング術です。 女性の「脳を健康を働かせる」!安心と安らぎを分かち合う、が教育のテーマと目標です。「気持ちが安心する。だから、知的に考えられる」という女性の本質を支えつづけるカウンセリング術です。
女性の「脳を健康を働かせる」!安心と安らぎを分かち合う、が教育のテーマと目標です。「気持ちが安心する。だから、知的に考えられる」という女性の本質を支えつづけるカウンセリング術です。 女性の脳の働きが伸ばす「人格=パーソナリティ」を目ざましく発達させる!が教育の方針です。
女性が社会性の世界(学校・仕事・社会の規範・人間関係のルール・合理的な思考)と、知的に関われる!を一緒に考えつづけるカウンセリング術です。
女性の脳の働きが伸ばす「人格=パーソナリティ」を目ざましく発達させる!が教育の方針です。
女性が社会性の世界(学校・仕事・社会の規範・人間関係のルール・合理的な思考)と、知的に関われる!を一緒に考えつづけるカウンセリング術です。 ストレスを楽々のりこえる女性の「脳」を育てる!!が教育の人気の秘密です。女性は、脳の働きと五官覚の働き(察知して安心。共生して気持ちよくなる)とぴったりむすびついて、一生、発達しつづけます。
ストレスを楽々のりこえる女性の「脳」を育てる!!が教育の人気の秘密です。女性は、脳の働きと五官覚の働き(察知して安心。共生して気持ちよくなる)とぴったりむすびついて、一生、発達しつづけます。  人の性格(ものの考え方)が手に取るように分かる「心の観察学」
人の性格(ものの考え方)が手に取るように分かる「心の観察学」 心の病いに感染させられない「人間の関係学」がステキに身につきます。
心の病いに感染させられない「人間の関係学」がステキに身につきます。 心の病いを救出する、心と心をつなぐ「夢の架け橋術」
心の病いを救出する、心と心をつなぐ「夢の架け橋術」 相手に好かれる「対話術」がまぶしく輝くので、毎日が心の旅路。
相手に好かれる「対話術」がまぶしく輝くので、毎日が心の旅路。 相手の心の働きのつまづきが正しく分かって、「正しい心の地図をつくれる」ので、損失、リスクを防げます。
相手の心の働きのつまづきが正しく分かって、「正しい心の地図をつくれる」ので、損失、リスクを防げます。 学校に行くとイジメがこわいんです。私にも原因ありますか?
学校に行くとイジメがこわいんです。私にも原因ありますか?  怒りっぽいんです。反省しても、くりかえしています。治りますか?
怒りっぽいんです。反省しても、くりかえしています。治りますか?  「仕事・人生・組織に活かすカウンセリング」です。他者の心身のトラブルを解消できれば、自然に自分の心身のトラブルも解消します。
「仕事・人生・組織に活かすカウンセリング」です。他者の心身のトラブルを解消できれば、自然に自分の心身のトラブルも解消します。 プロ「教育者」向けのカウンセリング・ゼミです。
プロ「教育者」向けのカウンセリング・ゼミです。 「脳の健康を向上させる」、が教育のテーマと目標です。「指示性のカウンセリング」は、「考えたことを実行し、考えないことは実行しない」
という人間の本質を、最後まで励まし、勇気づけるカウンセリング術です。
「脳の健康を向上させる」、が教育のテーマと目標です。「指示性のカウンセリング」は、「考えたことを実行し、考えないことは実行しない」
という人間の本質を、最後まで励まし、勇気づけるカウンセリング術です。 脳の働きがつくる「人格=パーソナリティ」を育てる!が教育の方針です。
脳の働きがつくる「人格=パーソナリティ」を育てる!が教育の方針です。 ストレスに強い、元気に働く「脳」に成長させる!!が教育の魅力です。
ストレスに強い、元気に働く「脳」に成長させる!!が教育の魅力です。 「心の病いの診断学」が楽しく身につきます。
「心の病いの診断学」が楽しく身につきます。 心の病いの予防と解消の仕方の「人間の理解学」が身につきます。
心の病いの予防と解消の仕方の「人間の理解学」が身につきます。 心の病いに気づける「人間への愛情学」が驚くほど身につきます。
心の病いに気づける「人間への愛情学」が驚くほど身につきます。 「交渉術」の知性と対話の能力が目ざましく進化しつづけます。
「交渉術」の知性と対話の能力が目ざましく進化しつづけます。 相手の心の病理が分かって、正しく改善できるので心から喜ばれます。「心の診断術」
相手の心の病理が分かって、正しく改善できるので心から喜ばれます。「心の診断術」 病気になるということ、病気が治るということが正しく分かる、最高峰の知性が身につきます。
病気になるということ、病気が治るということが正しく分かる、最高峰の知性が身につきます。 朝、起きると無気力。仕事にヤル気が出ません。うつ病でしょうか?
朝、起きると無気力。仕事にヤル気が出ません。うつ病でしょうか?  仕事に行こうとおもうと、緊張して、どうしても行けません。治りますか?
仕事に行こうとおもうと、緊張して、どうしても行けません。治りますか? 






