| 川村敦子(仮名・30歳)のうつ病」 |
| ●二○○二年に診断 |
| (1) |
川村敦子(仮名・30歳)は、地方都市のアパートで大学生の同級生だった夫(30歳)と二人暮しだ。二〇〇二年に「うつ病」と診断された。
今も、療養生活をつづけている。
川村敦子は、広告デザインの仕事をしていた。
入社して4年が経っていた。仕事は、締め切りに追われていた。
「まず、ご飯が食べられなくなった。食べて、吐く、という日々が1週間、つづいた。食べ物の匂いも気持ち悪くなった。夫に相談した」。
「あなたの最近の様子は、おかしい」(夫)。
「仕事を止めたい、死にたい、消えたい」とボロボロと涙をこぼして泣いたという。
夫と一緒に「心療内科」を受診した。「うつ病」と診断された。
「仕事を休まなければ治りません」(医師)。
「はあ?」って感じだった。
「今、1ヵ月、仕事を休みなんてありえませんから」。
しかし、半信半疑ながら、休職した。 |
| ●うつ病の症状 |
| (2) |
川村敦子は、休職すると、とたんに混乱の日々に突き落されるようになる。
「2時に寝ようが、3時に寝ようが、必ず朝の4時に目が醒める。朝が早いと、電話もメールもできない。ものすごく孤独だった。
夜中まで仕事をしていた私が、一日中、家にいることじたいが屈辱だった。家事をする気にはなれない。本も読みたくない」。
「考えることは、ああ、面倒くさい、生きているのも面倒くさい、だった。私は、感謝されること、賞賛されることが自分の存在価値だと思っていた。これが無くなった。もう、地獄、地獄。地獄のロードだった」。
「いきつく結論は、あたしの精神が弱いから、だった。すべて私が悪い」。
「私の母親は、スーパー主婦だった。だから家事ができなくなった自分が情けなく、許せない。今日も、掃除をしなかった。洗濯はした。だが、ポケットにティッシュが入っていた。こんなことで生きているのが死ぬほど嫌になる。夫に、泣いて訴える。夫は、何も言えない」。
「時々、調子が良くなる。そんな時は本を読む。パソコンで検索してみる。
何をすれば、早く感謝されて賞賛されるそんな渦の日々に戻れるのか。パソコンの中にひたすら祈りをこめて求めた」。 |
| ●薬で治ったと思った |
| (3) |
慢性的な疲労感と自責感にさいなまれるだけの無気力な状態が、約数ヵ月つづいた。薬を変えたら、一定の改善が見られた。
二〇〇三年一月。
川村敦子は、限定的に職場に復帰することになった。心療内科の医師は、「出来ません。分かりません。今日は帰ります。この三つの言葉を言うように」と指導した。
川村敦子は、好不調の波に揺れ動きながら仕事をつづけた。 |
| ●退職 |
| (4) |
二〇〇四年十二月。
川村敦子は、退職して本格的な療養生活に入ることを決意する。
「結局、思考のパターンが全く、何も変わっていないから、出来ません、分かりません、帰ります、という言葉を言うことがものすごい緊張をもたらした。自分を優先するということがどうしてもよく分からない」。
「職場から、?うつ病の治療はそんなに長くかかるものではない?と暗に辞職を勧告された。その日の夜、夫が帰ってくるのを待って半狂乱になった。ギャーギャー泣いて喚いた」。
「辞めてやるーっ、死んでやるーっどうせ、あたしなんか生きていてもしょうがない!」。
夫は、一晩中、「だいじょうぶだよ」と慰めてなだめてくれた。
私は、夫が眠った一瞬の隙に「今だって、2週間分の薬を全部、お酒で飲んだ」。
もう、べろん、べろん、どろん、どろんになった。「気がついたら病院のICの部屋の中だった」。
退職のきっかけはこの自殺未遂だった。 |
| ●自傷行為 |
| (5) |
「じつは、それまでも、支障のない範囲で自傷行為はやっていた。自分の存在が許せない、不快感でいっぱいになる、そんな時に自分を痛めつければいいと、自傷する」。
「心の底には、自分は?見捨てられている?という不安が冷たく固まりになって目を光らせている。その目と目が合う。
そこで演技をする。自分を攻撃してみせて、こんなに立派じゃないか、あんなにすばらしいじゃないかって評価と賞賛をねだる」。
「主婦は、人間関係が希薄になる。夫との関係もしだいに希薄になる。恋愛の時代には思ってもみなかった。夫に責められるとか、幼い子どもという逃げられない存在がいる人の場合、残された選択肢は、自分を攻撃することしかなくなる」
|
| ●薬でもうろうと |
| (6) |
「今は、布団に入っても寝つけない。もんもんとして考える。いつ仕事に戻れるのか、今後、自分はどう なっていくのか。ものすごく不安になる。悲しくなる。思考を総動員して自分の何がいけなかったか?をぐるぐると探す。そのうちに身体を起こすことができなくなる。どの筋肉をどう使えばいいのか?動かし方を思い出せなくなった。
朝になる。夫が、口に薬を流し込む。
薬でもうろうとしてただ横になっているだけの日々が過ぎていく。辛いという感情が脳の真ん中あたりに湧き上がってくる。それがあふれてきて、耳や目に流れてくる。耳腫れになっている。目からもあふれて目をふさいでいる」。 |
| ●パソコンで |
| (7) |
「うつ病は、心の病気というより も一時的な脳の機能障害といわれた。脳内神経伝達物質のバランスが乱れて、落ち込む、悲しい、不安だ、などの感情をコントロールできなくなる病気だとも。ストレスによる一時的な脳の機能障害だって。うつ病は、心の風邪といわれているって。それほど身近な病気だって。だから必ず治る病気だから薬を飲むこと、休養が不可欠と、ノートパソコンで、うつ病の主婦仲間と交信し合ってい る」 |
| ●「いいことがありますように」
|
| (8) |
川村敦子は、4畳半の和室で一日を過している。淡いグリーンのギンガムチェックのカーテン、黄色のラ ブチェアー、小さな食器棚がある。日本のテーブルと二脚のイスがある。「薬入れの箱」は動物の小さなぬいぐるみだ。アロマやお香もある。いいことがあった時にと、コインを入れる貯金箱もある。薬箱の側に置かれている。
「こんなに貯まっているよ」って分を励ますためだという。コインは箱の半分近くまでぎっしりつまっている。 |
| 吉田志保(仮名・40歳)のうつ病 |
| ●二○○五年五月 |
| (1) |
吉田志保(仮名・40歳)は、二〇〇〇年五月に精神科によるうつ病の治療が始まった。
住いは、山村留学で訪れた土地にある。
山村留学の時に知り合った今の夫と結婚して、住みついた。家族構成は、夫と6歳の長男と3人だ。
「私の母親は、兄を溺愛しててんよ。
“あんたは、お兄ちゃんに恵まれてよかったやないか。お兄ちゃんのために男の子を産みたかったんやけど、生まれてきたんは、女の子のあんたや”と言われた。“わたしの身体が弱いんはあんたのせいや”ってようなじられた。“あたしがボロボロになったんは、あんたが栄養を吸い取ったんや”」。
母親の口癖は「お母ちゃん、やさしくていい人やろ。天使みたいやろ」だった。
「ようできひん」という母親のために私は、小学生の頃から、大人のように一人で買い物に行った。食堂で一人でご飯を食べた。親戚にお中元を届けた。私は何でもできる子やってん」。 |
| ●生育歴 |
| (2) |
吉田志保は、手のかからない、家の仕事も学校の勉強もがんばる優等生だった。
学級委員もやった。母親の言葉にしたがって大学卒業後は、中学の教員になった。
24歳の時に「結婚しよう」という相手があらわれた。結婚の日取りも決まった。
母親が言った。
「志保ちゃん、私、血を吐いたわ。あんた、結婚止めるって言ってくれるか?そしたら治るんやけどな」。
母親に毎晩、言われた。精神的に耐えきれずに、自分で結婚を破談にした。 |
| ●31歳 |
| (3) |
31歳になった。
母親からの呪縛から逃れようと、「山村留学」という名目で家を出た。
一九九八年。33歳で結婚した。次の年に長男が生まれた。 |
| ●ショック |
| (4) |
「子どもが0歳8ヵ月の時、父親が死んだ。実家の片づけを一人でやっていた。
子どもが高熱を出して病院にも通っていた」。
母親が「あんた、いつまでここに居座る気やの?さっさと出て行って!」と言った。ショックだった。 |
| ●ヘルペス |
| (5) |
吉田志保は、帰宅すると「帯状疱疹」(ヘルペス)で入院した。
「入院中に、学童保育の指導員になるために履歴書を書いとった。もともと社会復帰したかった。母親との関係で疲れていたから違うところに飛び出して気分を変えたかったんやね」。
働き始めたらよくなると思っていたのに、ガンガンと、ものすごい頭痛がつづいた。「鎮痛剤を飲んでも全く治らへんねん」。
夫が、「ゴールデンウィーク、楽しみだね」と言った。いつもなら「そやね」と言う私が「ごめーん、あたし、楽しくないねん」と答えた。この瞬間、「あたし、調子悪いわ」って気づいた。夫に「精神科に行っていい?」と言った。
初めて精神科を受診した。 |
| ●「嬉しかった」 |
| (6) |
精神科医から言われた。
「お母さんのことは、かなりひどいものがある。子育てだけでも大変なのに、慣れない土地で本当によくがんばってきましたね」。
この言葉はとても嬉しかった。
「罪悪感をもたないで子どもを園に預けたまま、身体を休めてください」と言われた。うつ病の投薬を開始して、仕事は辞めた。 |
| ●イライラは夫にぶつける |
| (7) |
「ひどい時には、全く何もできない。ただ、ソファに横になっている。窓の外の風景をぼんやりと眺めるだけしかできない。
長男が遊ぼうと言えば、身体の上に乗せるのが精一杯やねん。夫に、“ごめーん、何か食べさせて”と全部、家事をやってもらう日々になった」。
「そこまで落ちていない時は、子どもだけは何とか、やらなと思ってて。身体を使った遊びはできない。絵本を読むことはできた。食事を作るのは無理やった。コンビニ弁当、お惣菜を夫に買ってきてもらう。
辛くても、イライラは子どもにはぶっつけなかった。イライラは、夫にぶっつけた」。 |
| ●子どもの幼稚園 |
| (8) |
ある日、息子が幼稚園に行くのをぐずった。
こちらもしんどくて動けない。9時までに登園せなあかんのに、10時になっても“休みます”の電話ができひんねん。身体が固まって動かへん。そのまま1時間がすぎた。どう しよう、どうしようと、どんどん落ちていく。薬を16分やった。
もう、幼稚園こわい、幼稚園こわい、こわいよーってそれだけがガンガンと頭の中でいっぱいになった。夫が帰ってきて、なんとか戻った」 |
| ●義母 |
| (9) |
「夫の母、義母が近くにいる。お米もとげなくなった、と病気のことを話した。
“夕食、食べに来るかい?”て誘ってくれた。好意に甘えた。その後、電話がかかってきた。“ところで、いつ治るんだい?いつまでも甘えてんじゃないよ。がんばりなさいよ”
“甘えでも、わがままでもなくて、気力がなくなる病気なんです”と言うのが精一杯だった。電話を切ったら、涙があふれてきて止まらんかったわ」。 |
| ●全く動けない |
| (10) |
最近、ようやく、料理を作れなくてもいいやって開き直れた。無理してカリカリ作るよりも、休んでる方が早く作れる日がやってくるやろなって。
義母のことも受け流せるようになった。幼稚園の役員も断った。引き受けたら自分の容易を超えてやってしまうのが目に見えているから。
夫は、私が動けなくなると、よかったねと言う。動けなくなるまで必死に無理してやりつづけるからなんやて。休む勇気をもつことが大事なんだと、今、本当にそう思っている」。 |
| 山下真由(仮名、35歳)の うつ病 |
| ●一九九六年六月 |
| (1) |
山下真由(仮名、35歳)は、一九九九年六月に「うつ病」と診断された。
二〇〇二年三月まで闘病生活を送った。
現在、2歳の娘の母親である。職業は、「元・研究者」である。 |
| ●家事 |
| (2) |
「今、思えば、引っ越しうつ病だったと思う。結婚して、知らない土地に来た。
友人もいない。家事と研究に明け暮れて忙しい日々だった。
いっしょうけんめいに慣れない家事をやった。そのハードルはものすごく高かったのだろうと思う。今まで、困難は努力すれば報われてきたから。
家事も努力すれば報われると思ってやってきた」。
「夫は、入社して一年目で、自分のことで精一杯だった。今までは、がんばれば結果を出せた。ところが、なぜ、うまくいかないのか、分からない。自分を責める気持ちになる。思い詰めるように家事をやった。
ある日、午前中、ベッドから起き上がれなくなった」。
医者から「うつ病」と診断された。
「なんだ病気だったんだ」と、ホッとした。病気なら治れば、また努力して結果を出せる。 |
| ●実家で |
| (3) |
「実家に帰った。すると、寝たきりの状態になった。脳から身体の命令系統の全てが壊れた」。
「実家の住所すら思い出せない。
手が震えて字も書けない。頭がボーッとして何も考えられない。ただ寝ているだけになった」。
「突然、身体の中から激しい感情が噴き出してくる。赤ん坊のように泣いてわめく。感情にまかせてただ、泣くだけになった」。 |
| ●メモ |
| (4) |
「枕元にメモ用紙だけは置いていた。今日、何をしたか、それだけでも書き止めようと思った。研究者の訓練のせいかな。
“トイレに行った”と一行しか書けない日もあった」。
|
| ●パソコンで |
| (5) |
「起き上がれる日は、本を読んで、パソコンで検索して、病気のことを知ろうとした。今までの自分と全然、違う自分になったのは、なぜなんだ?と」。
|
| ●うつ病の正体 |
| (6) |
「私が知りたかったのは、生活レ ベルでうつを生きるとはどういうことなのか?しかも、主婦という立場でのうつとは?ということだった。それは、どこにも見つからなかった。だから、書かなければだめだと思った。自分は、確かにおかしいけれど どういう状態になっているか、一〇〇%、患者の立場で書く。
とても辛い作業だったけど、病気を客観的に突き放すことができたと思う。苦しいけど、正体を捕まえているから大丈夫と思えた」。
|
| ●三ヵ月 |
| (7) |
「うつ病」という診断から三ヵ月が過ぎた。「闘病記」を書き上げてネットの上に置いた。
「同じ経験をしている人がきっといるはずだ、と思った。絶対に、誰かいるはずだ、気持ちを分かってくれる仲間が、って。誰かとつながりたかった」。
|
| ●寂しさ |
| (8) |
「主婦のうつ病の本質は、寂しさ、なのだと思う。とにかく社会とつながっていない。こんな自分は価値がない。
孤独だっていう寂しさ。寂しさが堂々めぐりをする。こんな寂しさがつづくなら消えてしまいたいって思う」。
「夫が、側にいないという寂しさではない。
ずっと側にいてほしいという寂しさではない。自分が生きていることに意味がない、社会の中で価値をもっていないという孤独感の寂しさだ。これが、主婦のうつ病の中核にあると思う。ふだんは、この観念の中をぐるぐる回っているけれども、たまに遠心力で外に出ると、自傷行為、自殺未遂をやってしまう」。
山下真由の手首にも傷跡がある。 |
| ●サイト |
| (9) |
「うつ主婦のためのサイトを立ち上げた。
うつ主婦の仲間が、寂しさや孤独を癒してくれた。掲示板は救いだった。
お互い、行動レベルのことしか書けない(書きたくても書けない)けれど、“久しぶりに晴れたねえ。洗濯できなかったけど”だけで梅雨の晴れ間に洗濯できなかった自分なんか死んじゃえばいいという“孤独”が分かる。
だって、同じだから。そうやって繋がることで、一人じゃないって確認し合えてホッとするんです」 |
| ●自分を変えること |
| (10) |
「うつから回復することとは、元に戻ることではなく、作り直すこと」と山下真由はいう。
「サイトに、簡単料理とか、手抜きのコツなど“生活の知恵コーナー”を作った。うつを生きるには、どういう思考がいるのか?を示したかったから。
料理一つでも、今までと違う解決の仕方を探すことで考え方を変えてほしいと思う。
このうつ病は、自分が変わらないと治らない。それは、自分を変えていくしかないものだから」。
山下真由は、「橘由歩」が取材した中で唯一のうつ病卒業者である。 |



 ケーススタディー
ケーススタディー ポルソナーレ式セカンドステップ26
ポルソナーレ式セカンドステップ26 ハーバード流交渉術
ハーバード流交渉術 『ドキュメント・主婦のうつ病』
『ドキュメント・主婦のうつ病』 第43回・浅見鉄男主宰「簡易井穴刺絡学」
第43回・浅見鉄男主宰「簡易井穴刺絡学」 『脳、100の新知識、その形態から新知識まで』
『脳、100の新知識、その形態から新知識まで』 『脳内麻薬と頭の健康』
『脳内麻薬と頭の健康』





 トップページ
トップページ  NEW! 年間カリキュラム
NEW! 年間カリキュラム  学習の感想と学習成果
学習の感想と学習成果  「日本人の思考」と「谷川うさ子王国物語」と「グローバル化の恐怖」
「日本人の思考」と「谷川うさ子王国物語」と「グローバル化の恐怖」 学習内容(サンプル)
学習内容(サンプル)  「言葉」 日本語の影響。その仕組みと感情、距離感、人間関係について
「言葉」 日本語の影響。その仕組みと感情、距離感、人間関係について

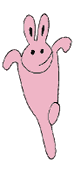
 「女性向け」、「男性の“女性”対応」のカウンセリング・ゼミです。
「女性向け」、「男性の“女性”対応」のカウンセリング・ゼミです。 女性と心を分かち合える「脳」を、最高に発達させる!!が教育の狙いと目的です。女性を「見る」「見たい」、女性から「見られる」「見られたい」関係をつくる、カウンセリング術です。
女性と心を分かち合える「脳」を、最高に発達させる!!が教育の狙いと目的です。女性を「見る」「見たい」、女性から「見られる」「見られたい」関係をつくる、カウンセリング術です。 女性の「脳を健康を働かせる」!安心と安らぎを分かち合う、が教育のテーマと目標です。「気持ちが安心する。だから、知的に考えられる」という女性の本質を支えつづけるカウンセリング術です。
女性の「脳を健康を働かせる」!安心と安らぎを分かち合う、が教育のテーマと目標です。「気持ちが安心する。だから、知的に考えられる」という女性の本質を支えつづけるカウンセリング術です。 女性の脳の働きが伸ばす「人格=パーソナリティ」を目ざましく発達させる!が教育の方針です。
女性が社会性の世界(学校・仕事・社会の規範・人間関係のルール・合理的な思考)と、知的に関われる!を一緒に考えつづけるカウンセリング術です。
女性の脳の働きが伸ばす「人格=パーソナリティ」を目ざましく発達させる!が教育の方針です。
女性が社会性の世界(学校・仕事・社会の規範・人間関係のルール・合理的な思考)と、知的に関われる!を一緒に考えつづけるカウンセリング術です。 ストレスを楽々のりこえる女性の「脳」を育てる!!が教育の人気の秘密です。女性は、脳の働きと五官覚の働き(察知して安心。共生して気持ちよくなる)とぴったりむすびついて、一生、発達しつづけます。
ストレスを楽々のりこえる女性の「脳」を育てる!!が教育の人気の秘密です。女性は、脳の働きと五官覚の働き(察知して安心。共生して気持ちよくなる)とぴったりむすびついて、一生、発達しつづけます。  人の性格(ものの考え方)が手に取るように分かる「心の観察学」
人の性格(ものの考え方)が手に取るように分かる「心の観察学」 心の病いに感染させられない「人間の関係学」がステキに身につきます。
心の病いに感染させられない「人間の関係学」がステキに身につきます。 心の病いを救出する、心と心をつなぐ「夢の架け橋術」
心の病いを救出する、心と心をつなぐ「夢の架け橋術」 相手に好かれる「対話術」がまぶしく輝くので、毎日が心の旅路。
相手に好かれる「対話術」がまぶしく輝くので、毎日が心の旅路。 相手の心の働きのつまづきが正しく分かって、「正しい心の地図をつくれる」ので、損失、リスクを防げます。
相手の心の働きのつまづきが正しく分かって、「正しい心の地図をつくれる」ので、損失、リスクを防げます。 学校に行くとイジメがこわいんです。私にも原因ありますか?
学校に行くとイジメがこわいんです。私にも原因ありますか?  怒りっぽいんです。反省しても、くりかえしています。治りますか?
怒りっぽいんです。反省しても、くりかえしています。治りますか?  「仕事・人生・組織に活かすカウンセリング」です。他者の心身のトラブルを解消できれば、自然に自分の心身のトラブルも解消します。
「仕事・人生・組織に活かすカウンセリング」です。他者の心身のトラブルを解消できれば、自然に自分の心身のトラブルも解消します。 プロ「教育者」向けのカウンセリング・ゼミです。
プロ「教育者」向けのカウンセリング・ゼミです。 「脳の健康を向上させる」、が教育のテーマと目標です。「指示性のカウンセリング」は、「考えたことを実行し、考えないことは実行しない」
という人間の本質を、最後まで励まし、勇気づけるカウンセリング術です。
「脳の健康を向上させる」、が教育のテーマと目標です。「指示性のカウンセリング」は、「考えたことを実行し、考えないことは実行しない」
という人間の本質を、最後まで励まし、勇気づけるカウンセリング術です。 脳の働きがつくる「人格=パーソナリティ」を育てる!が教育の方針です。
脳の働きがつくる「人格=パーソナリティ」を育てる!が教育の方針です。 ストレスに強い、元気に働く「脳」に成長させる!!が教育の魅力です。
ストレスに強い、元気に働く「脳」に成長させる!!が教育の魅力です。 「心の病いの診断学」が楽しく身につきます。
「心の病いの診断学」が楽しく身につきます。 心の病いの予防と解消の仕方の「人間の理解学」が身につきます。
心の病いの予防と解消の仕方の「人間の理解学」が身につきます。 心の病いに気づける「人間への愛情学」が驚くほど身につきます。
心の病いに気づける「人間への愛情学」が驚くほど身につきます。 「交渉術」の知性と対話の能力が目ざましく進化しつづけます。
「交渉術」の知性と対話の能力が目ざましく進化しつづけます。 相手の心の病理が分かって、正しく改善できるので心から喜ばれます。「心の診断術」
相手の心の病理が分かって、正しく改善できるので心から喜ばれます。「心の診断術」 病気になるということ、病気が治るということが正しく分かる、最高峰の知性が身につきます。
病気になるということ、病気が治るということが正しく分かる、最高峰の知性が身につきます。 朝、起きると無気力。仕事にヤル気が出ません。うつ病でしょうか?
朝、起きると無気力。仕事にヤル気が出ません。うつ病でしょうか?  仕事に行こうとおもうと、緊張して、どうしても行けません。治りますか?
仕事に行こうとおもうと、緊張して、どうしても行けません。治りますか? 






