| 日本人の心の病いの原型は人間関係です |
昭和52年に刊行された『対人恐怖の人間学』(弘文堂・刊)という本があります。帝京大学医学部・精神医学の助教授(当時)の内沼幸雄が書いています。
この「昭和52年」の当時にとらえられた対人関係の病理を今ご紹介するのは、日本人の対人意識のものの考え方は全く変わっていないことを確かめるためです。
内沼幸雄は、次のように書いています。
① 昭和42年度、京都大学入生
2、481名にたいしてUPIという質問による調査をおこなった。(稲浪正充、笠原嘉による)。
結果は次のようなものだ。
赤面しやすい…995人(40・1%)
他人の視線が気になる…798人(32・2%)
吃ったり、声がふるえる…239人(9・6%)
変な匂いがする…51人(2・1%)
不眠がちである…458人(18・5%)
頭痛がする…597人(24・1%)
この調査では、「この一年間のうちに一度でも体験されていれば」「気楽にマークしてください」と指示している。だから、数値そのものが必ずしも病理学的に病的であることを意味しない。
その後のサブクリニカルの面談をとおして病的な範囲を限定すると、結果は次のようなものだ。
赤面症…3名
視線恐怖症…2名
体臭恐怖症(自己臭パラノイア)…3名 |
| 日本人は「対人恐怖」を抱えている |
この調査からくみとれることは次のようなものだ。
- この調査結果は、「対人恐怖症的症状」を欠いている「対人恐怖症」の存在を示している。
- 「対人恐怖の症状」と同じものを「正常者」の中にまで捜し求めて得られた結果である。
- このような調査結果の傾向は、さらに日本人の精神構造の中に、広く、深く浸透しているものと思われる。
② 「地獄とは、他人だ」とはサルトルの言葉である。対人恐怖は、「他人が地獄となる疾患」である。
そして、対人恐怖とは「自分もまた地獄となる疾患」である。
③ 精神分裂病は「他人が地獄となる疾患」である。患者は、自分に救いを求める。
「躁うつ病」は「自分が地獄となる疾患」である。患者は、他人に救いを求める。
ともに救いが得られずに人格が解体する。この二大精神病の中間の要(かなめ)の位置にあるのが「対人恐怖症者」である。対人恐怖症者は、自分も他人も地獄となるために、自分と他者を超えたところに救いを求める。
④ 森田学派の高良武久は、日本人の対人恐怖についてこうのべる。
- アメリカでは対人恐怖症を主訴とする患者はきわめて少ない。このことを精神分析学者カレン・ホーナイとジョン・ハートに尋ねた。
欧米では対人恐怖についてくわしく記載したものはない、という回答を得た。
|
対人恐怖の症状のベスト10 |
- 対人恐怖症患者の訴える症状は、52項目ある。最も多い症状を10位まであげると次のとおりである。
1位・人とスムースに交わっていきたいがうまくいかない。
2位・自分の表情、態度が変だから、他人が変に思ったり嫌な顔をするので苦しくなる。
3位・時々、他人に悪い感じを与えたような気がして苦しい。
4位・他人の見ている所で、何かの動作をすると自分の動作がいちいち気になる。ぎこちなくなる。
5位・家の外、あるいは大勢の中に出ると、つねに他人が自分の顔や動作を注目しているように思う。
6位・少し親しくなった人、初めて会った人、異性、年上の人に対して恐怖を感じる。
7位・人にバカにされないか?軽く扱われないか?と敏感になる。
8位・視線のやり場に困る。目をそらす。相手の目を見ることができない。
9位・人と対立的になって苦しい思いをする。そのつもりがないのに、不快にさせることを言ったり、礼に欠くことを言って関係が壊れる。
10位・人が集まって話をする時、話せなくて孤立して辛い思いをする。
|
日本人は、他者を遠い対象と認知している |
■日本人にだけ特有の病理の対人恐怖は、一体なぜ日本人に生成されるのでしょうか。それは、日本人が使っている「日本語」に原因があります。日本語によって人間関係について考えているからです。
国語学者・大野晋の日本語(和語)の語源の研究によれば「対人不安や対人緊張、対人恐怖」をつくり出すメカニズムは、次のとおりです。
あらためてご一緒に確認してみましょう。
① 日本語には、日常の会話、あるいは手紙(現代ではメールも)の文章など、対人関係によって影響を受ける表現に「敬語」がある。「親しき仲にも礼儀あり」といわれているとおり、「敬語」は、相手と自分とをどう位置づけるか?という扱い方をあらわすものだ。「位置づけ」とは、相手を自分より「上か、下か」、「遠いか、近いか」の気配りを言葉づかいで表すものだ。
② 日本語では、相手を「遠い所にいる存在」として扱うことが敬意の一つの表現法である。(あなた。あなた様、など)。
③ 日本語では、相手を「内(ウチ)の存在」か、「外(ソト)の存在」かという意識がこまかく働いて人々は、この区別に非常に敏感に反応する。
④ 日本語(和語)をつくり出した古代の原始社会では、「内(ウチ)」は「安全な場所」であるととらえられていた。(安心できる、親愛できる、時には侮蔑にまで発展してもいい空間であるという意識)。
「外(ソト)」は「恐ろしい場所である」ととらえらえていた。(外(ソト)…遠い場所。恐怖の位置。自分に左右できないこと、自分が立ち入るにはリスクが大きいところ、成り行きにまかせて手を加えないものだ、という意識)。
|
| 日本人にとって他者は、「人格」の無い存在である |
■このような日本人の使う日本語が、なぜ「対人恐怖」を生むのでしょうか?理由は、日本人は、人間というものを「遠い空間」か「中くらいの距離の位置にいる存在」か、もしくは「自分のいる空間の中に位置している存在」か、というように了解するということにあります。日本人は、人間を「空間の中の存在」と認識して、「意思をもつ主体」とは理解しません。
このことについて言語社会学者・鈴木孝夫は、次のように書いています。
① 英語では、母親が幼児にたいして、自分をI とかmeと自称することがある。これは、子どもを無力な存在とは見ないで、自分に対立する一個の人格として見る場合である。
② 西欧諸国で見られる人称代名詞は、きわめて主観的・心理的なものである。自分のまわりの人間・事物を、自分の正規な言語上の相手と見るか、同等の資格で言葉を交わせるかどうかが、二人称か、三人称かを分ける基準になる。
③ 日本語には「人称」という範疇(はんちゅう)が存在しない。日本人は、話の相手との心理的な対決を避けたいか、恐れている。
一見して二人称のように見える「あなた」「おまえ」「そちら」などは、相手のいる場所を言っている。相手を間接的に暗示して指している。
日本語には、西洋の言語でいうような「二人称代名詞」は存在しない。
しいて人称代名詞という用語を用いるならば、日本語では、私、俺を含めて全て「三人称」というしかない。
(『日本語万華鏡』「人称の本質は何か」『新潮45』2009・1月号より) |
| 日本人のものごとの分かり方は「メトニミー」という思考の方法である |
■すると、日本人は、家の中の家族との会話でも、相手を「人格をもった主体」「意思をもった主体」とは見なしていないことが分かります。話されている言葉は、「自分のいる位置」にいるかどうかをチェックして気持ちの安心の相互交流をおこなっています。
それは、「言葉によるコミュニケーション」によるものではなくて、「目で見る」という視覚によるイメージづくりという方法です。
会話は、「花は桜木、人は武士」の文の型に見られるように、断定や説明を避けて、曖昧な表現をおこなうという方法で自分の位置に融合させたり、取り込む、という関係づけをおこなっています。「曖昧な表現」は個別的、具体的な説明が無いということです。「おおよそのところ」「大体のところ」を言いあらわすことです。
「台所にあるもの」「風呂場にあるもの」「あれをもってきて」「あれはやりましたか」「あれをしませんか」などのような表現が「おおよそのところ」、「大体のところ」のことです。具体的なことを抽象的なカテゴリーに置き換える表現の仕方のことです。このような表現は、「相手が何を言っているのか?」を察知することが求められています。「相手の気持ちが分かる」「相手の気持ちを感じ取る」「その場の空気を読む」などの関係が成り立つことがお分りでしょう。
このような表現の仕方のことを「メトニミー」(metonymy・換喩)といいます。「お膳」(ととのえた食事)、「四つ足」(けもののこと)、「赤ずきん」(赤ずきんをかぶっている女の子)、「たこ焼」(たこを入れたお好み焼き)などがメトニミーです。メトニミーとは、「Aのもの」を「B」に取り込んで「B」に融合させる、という手法のことです。日本人は、人間関係を「メトニミー」という換喩の方法で他者を自分に融合させて同化させてきました。
「あの人が気になっています」「あの人に好意の気持ちをもっています」「あなたのことがずっと気になっていました」「あなたの姿をずっと思い浮べてイメージしていました」などが日本人の対人意識のメトニミー(換喩)による取り込み方です。
このような日本人の対人意識が、なぜ対人恐怖症をつくり出すのでしょうか?
内沼幸雄の『対人恐怖の人間学』の中からケーススタディをとりあげてご一緒に考えてみましょう。 |
ケース・1
人前でドキドキして楽しくない中学生の女の子 |
女性。中学生。小さい頃から気が小さくて人見知りがちだった。人前ではすぐにドキドキしてしゃべれなくなる。しかし、負けず嫌いで勉強はよく出来た。クラスでは二番の成績だった。二ヵ月前に先生からテストの成績が悪いと言われてドキドキしてしまった。これ以来、人前でドキドキするようになった。その後、学校に行きたくないと父親に話した。理由は、友人といても楽しくない、勉強もしたくないの二点だった。
〔解説〕
ここでは「遠い所にあるもの」は学校の教師やクラスの生徒です。
間関係は、言葉によって成立します。この言葉には内容があります。相手と自分を仲立ちさせるものが言葉です。この中学生の女の子には人間関係とは、言葉を仲立ちにして成立するという認識がなかったのです。学校での言葉は、勉強のことや学力の向上のことが内容になって対人関係を仲立ちさせるという認識がありませんでした。言葉の無い関係は、母と子、父と子の関係のように、一方的に自分の気持ちを安心させてくれる関係のことです。これは、「遠い所にいる人間としての学校の教師、クラスの友人」には近づかない、近づくと危険である、という日本人の「内(うち)の意識」による対人意識しか記憶されていないケースの対人緊張と対人不安の典型になります。
言葉が人間関係の仲立ちを成立させるというものの考え方が記憶されていない場合、全ての人間は、ドキドキする緊張の対象になります。相手が話しかけること自体が人間関係の中で「孤立を生む」という契機になります。
かくして、この中学生の女の子は、媒介性の意味と価値をもつという「学校の勉強」にも自分を安心させるという意義を見出せずに、学校からも孤立するに至っているのです。このケースでは、相手の話す言葉を記憶して、相手のものの考え方や相手の行動の意味を分かるということが全くの不成立という「うつの病理」を観察することが大切です。 |
ケース・2
男性の前で赤面する女性 |
女性。小さい頃から人見知りの傾向がつよくあった。高校の頃は、男性を意識して赤面することがあった。だが、男性の前では、大人っぽくふるまうようにしていた。
社会人になって赤面を意識するようになった。赤面を意識して会社の食堂で食事がとれなくなった。
仕事中に人から見られていると計算もできない。電車の中で、赤面することを怖れて座席に座れなかったこともある。
人と会って話すと、沈黙や白けることを怖れて、無理して明るくふるまい、自分からおしゃべりをする。そのために対人関係にひどく疲れる。この対人関係の不安のために仕事を次々と変えた。今は、小さな商店に勤めている。自分では「ひどく臆病な性格だ」と思っている。
「しかし、負けず嫌いなところもあり、切羽詰ると自分でも驚くほど大胆になる」と話す。 |
〔解説〕
ルール、きまりという共同幻想が無い観念 |
このケーススタディで注目しなければならないことは何でしょうか。
「高校」や「会社」「仕事」などは、「明治」になって以降、日本に導入された近代社会の教育制度や、近代資本主義の資本制度です。しかし、すでに皆さまもよくご存知のとおり、日本人は「日本語(和語)の文法」で「人間関係」を考え、行動しています。和語(日本語)は、大野晋の学的な考察によれば、「古墳時代の晩期」「弥生時代」に生成されて「音韻」や「文法」の体系が完成されています。その特徴は、目の前にいるどんな親しい人間と会話するときにも、「相手の人格的な主体」を不問にするというものです。
ケーススタディの女性の観念は「古代原始社会」の行動意識と、近代日本の国際社会の制度の意識との二つで二重になっていることがお分りでしょう。
この女性の観念の中に恒常的に表象されている「行動地図」には、社会の中のルールや社会の中で会話するときのコミュニケーションのルールなどの「言葉」はありません。
行動というものは、近代社会の中では「ルール」という秩序によって成り立つものだという明確なものの考え方がない、ということです。あるのは、自分の生理的身体が「性」としての「女性である」という意識だけです。「行動する主体」としての「自分」というものの考え方の中には、「自分が性としての女性である」という考え方は抽象化されて第二義的な意味しかもちません。このケーススタディの女性は、もちろん、表面的には「高校に行く」とか「会社に行く」などの行動はおこなっています。しかしその行動は自分の「観念」の中に「自分という主体がある」「自分という人格がある」「自分という心や精神をもつ意思の主体がある」という「共同幻想の表象」ではありません。
「共同幻想」とは、「行動地図」のようなイメージスキーマのことです。近代的な社会の中に生きる人間の「共同幻想」は、「近代社会」が「法秩序の体系」で整備されていることからも分かるとおり、ルールや約束、きまりごとの言葉とその意味を学習して、そのルール、約束、きまりごとの言葉とその意味を「行動地図」(イメージスキーマ)とすることが必要です。このような「行動地図」を自分の主体意思の「自己責任」において社会の中の「他者」と合意するという「共同幻想」を恒常的に表象させることが必要です。 |
| 行動が止まる意識が自分の「性」を相手に差し出す |
| しかし、ケーススタディの女性の観念には、「主体意思」によって「行動する」というイメージスキーマはありません。
この女性の観念に表象されているのは「行動しない自分」です。
あるいは、「行動することを不服に思っている自分」です。そのような「自分」とは、単なる「性としての自分、性としての女性である自己」のイメージスキーマです。
このイメージスキーマが「赤面」の原因になっています。この女性は、男性から見られるときは、仕事の中の自分という存在は単なる記号性の意味しかもたなくて、「行動が止まっている存在である」というイメージを「男性が見ている」と錯誤しているのです。そのような「性としての自分が見られている」と思えば、仕事の中でも食堂の中でも孤立する意識になることは、みなさまにもよくお分りでしょう。しかし、リアルな現実の中の男性と女性は、全員、近代資本主義の社会秩序の形式にのっとって行動しています。共同幻想は、どの日本人にとっても二重であるということはともかく、このケーススタディの女性は、自分の人生は自分でになって自己責任で決定して、そのとおりに行動すべきものであることはよく分かっているので、他の女性も男性も近代資本主義の社会制度に適応しているようにしか見えません。このような心的な現実の中で、自分だけが「性としての女性」を露わに鮮明にさせていると思えば、ここで抑制とその抑制のハネ返しの二つの意識が働いて、「赤面する」のです。このようなアジア型の共同幻想をつくる「X経路」の「行動停止」がいつでもどこでも優先している、というのがケーススタディの女性の「うつの病理」の内容です。このような「遠いところにあるもの」イコール「近代日本の資本主義のメカニズム」を「手を加えない」「近づかない」(勉強しない、学習しない、言葉を憶えない)と強固に思い込んで無視するところから「人が見ていると仕事の中の計算もできない」という「他者の眼」を「恐いもの」と想定した分裂病が派生します。このケーススタディは、このような病理として理解することができます。そして、このような日本人の観念の二重のメカニズムは、現在の日本のグローバル・リセッションの中の「ポスト・グローバル・リセッションの経済社会」など想像することもできない、という孤立(うつ病)を噴出させていると理解することが大切です。 |
ケース・3
母親不在の男性がたどる人生 |
| 男性。小さい頃に母親が亡くなって二度目の母親に育てられた。家庭は暗かった。社会人になって、自分は自由だと思い、みんなのため、弱い人のためにがんばろうと思った。明るくて、話し好きな性格で、職場の行事活動にも自分からすすんで積極的に参加した。ある日、旅行に行った。電車の中で隣り合わせた女性と話した。話題がとぎれた。
話に詰まった。この時、頭に血がのぼりどぎまぎした。恥かしくて顔が赤くなった。このとき以来、人と話すとどぎまぎして顔が熱くほてるようになった。症状は悪化した。治療してくれるところに行った。自分と似たような症状の人がたくさんいることを知った。
症状を聞いているうちに、今までは無かった症状が出てくるようになった。顔がこわばる、目が吊り上がる、などだ。電車の中で、自分の変な顔が見られているように思えた。人と話すと、相手になにか気まずい思いをさせているようで、相手に悪いことをしているような気がして人との関係を避けるようになった。自分がみんなの中に入ると気まずくさせるので、人の話にも入っていけない。今では、気持ちもひねくれてしまい、全てに自信を喪った。生きていくことにも自信がない。毎日、外に出れば人に会う。朝、起きるのが苦しくなった。 |
〔解説〕
会話する能力が欠落する |
| このケーススタディの男性は、なぜ赤面症になったのでしょうか。「会話」とは、脳の働き方のソフトウェアのメカニズムでいうと「Y経路」の対象です。「相手」は、自分ではないのでその人なりの「ものの考え方」や「行動の意思」をもっています。遠くの位置に存在する「個としての主体」です。言語社会学者の鈴木孝夫は、欧米語の「人称代名詞」とは、意思をもつ主体どうしの合意や了解を目ざす「人権主体の表象のことだ」と説明しています。ケーススタディの男性は、このような「近代的な現代社会」のコミュニケーションのルールを全く知らなかったことが「赤面の原因」になっています。
会話とは、「キャッチボールのようなものだ」といわれています。
相手が投げかけた「言葉」をボールに見立てて、スムーズに相互交流させ合うのが会話です。「関係性」というテーブルの上に「言葉」というボールを転がして相手に提供するというのが会話です。
相手からやってきた「言葉」をしっかり手で受けとめる、相手の「言葉」というボールは、そのつどそのつど異なる意味と内容のボールであるので、その中身をよく確かめる、そして、その中身にふさわしいボールを再び「関係性」というテーブルの上に転がす…というものが「会話のルール」です。 |
| 母親が男の子を見離すとガマンして行動する力が貧困になる |
| 日本語は、鈴木孝夫のいうように、「相手の人間的な意識の主体」を不問にして「あなた」「私」「お前」などの人称代名詞ふうの関係概念をつくり上げています。このことは「目の前」に人物がいて、目に見えていても、「相手はいない」という認知を無意識に抱えているということを本質にしています。そこで、日本語で会話しようとすると、この「相手不在」に陥りやすい会話の関係をつねにガードしなくてはなりません。ケーススタディの男性は、生育歴の中で母親不在であったと書かれています。男性にとって母親とは、ガマンしていくうえで自分の気持ちを安心させる「記憶のソース」になります。母親不在は、ガマンして行動していく空間性の行動能力を低いレベルにとどまらせます。男性にとって女性は、広い意味で性の対象です。安心の享受の対象です。それは会話をする、媒介を介在させて関係性を構築する、というかかわりのルートの中に「安心」が介在します。このような女性との関係の中から、とりわけ会話が安心を供給するという相手が狭い意味の性の対象になります。男性は、これらの道のりを、母親からの安心の享受を支えにして「ガマンの力」の水準を上げて、女性との関係という「空間性の能力」を身につけていきます。ケーススタディの男性は、「X経路を中心とする母親のまなざし」を記憶のソースにしていなかったので、「近代資本主義の経済社会」に存在する「他者」に近づいていくという行動が、人生の初めにも、人生の中頃にも全く無くて、社会そのものから孤立しています。
「社会」は、和語(日本語)の文法にとっては「外」(ソト)にあるものです。「遠くに行くなよ」という禁制の言葉と、「遠くのものに近づけば危険だぞ」という禁制の声をさし出すものです。「遠くに行きさえしなければ、行動を可能とし、性の欲求の実現も保証しよう」という黙契の声を聞いたときから、ケーススタディの男性は、人との関わりを避けるようになったのです。
「赤面」にしろ「顔のこわばり、目の吊り上がり」は、自律神経の交感神経の過緊張による血流障害が原因です。経験同一化の法則にもとづくイメージにしたがってこの血流障害は発生します。人が自分を見ていると思い、トカゲの脳の中隔核の欲求の記憶の表象が封鎖されていると思えば「赤面」するし、「声」も欲求の実現を目ざしてヒステリー症状をあらわすのです。
|
| 「うつの病理」と交渉する交渉戦術のモデル |
■このケーススタディの男性を対象にした「ハーバード流交渉術」による交渉の仕方をご一緒に考えてみます。このケーススタディの男性の「孤立」(うつの病理)は、「行動できない」(話の中に入っていけない)というものです。
「行動を変えると生きていく自信も、社会の中で他者とまじわる自信も回復する」という価値がもたらされます。
このような観点から「行動を変える」ことを目的にした交渉戦術です。
《人と話すと赤くなる》という症状がもたらすマイナス面
- 人と会わないと赤面しなくてすむ。
- 人の話す中に入らないと、気まずい思いをさせなくてもすむ。人に迷惑をかけない。
- 仲間の中に入っていくと、甘えるし、悪い気がして申し訳なく思う。
注意
ここで注目していただきたいのは、人と話すための行動のマイナス面の数は三つです。ケーススタディを見ると、これ以上の数に相当するものはありません。
この点を確認して、次に、「人と会話することのプラス面」を考えて、その理由も明らかにします。もし、ケーススタディの男性が当事者としている時は、本人に合意を求めることを一つずつおこないましょう。
《人と話すという行動に変えることのプラス面(メリット)とその理由》
- 人と話すこと、および、女性と話すことは、恐いことではないことが分かる…
(理由。話し方のルールを分かって会話をおこなうと、安心する)
- 人と話すことは、相手に喜んでもらえることが分かる…
(理由。会話とは、共感したり励ましたり、共に行動することだから、相手に喜びを与える)
- 人と話すことは、見知らぬ相手とも会話がつづくことだ。だから、自信がつく…
(理由。生きていく人生は、見知らぬ他者との出会いを広げていくことだ。その好例が本を読むことだ。新しい知識との出会いがある。これが自分を豊かにする)
- 人と会って話すことは、自分にとって価値のある異性との出会いがあることだ…
(理由。女性は男性との出会い、男性は女性との出会いがあって個べつの人生の歴史を築いていく。生きた証(あかし)を打ち建てるということだ。人はこのようにして生きた人生をナットクする)
このように、プラス面(メリット)の数とその理由を、マイナス面の克服としてカウントしてみましょう。数が多いことと、理由が本人の価値意識に合致すれば、「うつの病理」も克服されるでしょう。 |
| 現実を発見する知性の学習モデル |
「ハーバード流交渉術」の交渉戦術のためには、相手にとってのプラス面(メリット)を想像する力が必要です。その想像力は、推移律のトレーニングで身につきます。次の学習モデルを参考にして、トレーニングしてみましょう。
|
| A=B、B=C、故にA=Cの推移律の学習モデル |
■エクササイズ
◎事例・1
A・風が吹けば桶屋(おけや)が儲(もう)かる
B・意味(遠山啓の「水道方式」で開発されている「タイル」に相当します)
思いもよらぬ所に影響が及んで、意外な結果を生じること。また見込みもないことを当てにすること。
大風が吹くと土ぼこりが人の目に入る。目が病んで失明する人が増える。すると失明した人が仕事をする。三味線用の猫の皮がたくさん必要になる。猫がいなくなる。するとネズミが増えて、家々の桶(おけ)をかじってだめにする。その結果、桶屋が大繁盛するという必然的な結果になる。
C・設問
用例として適切なものはどれでしょうか?もっともよいものを選んでください。
- アメリカ発の「金融システムのバブルの崩壊」は、日本の製造業の限界をもたらした。これこそが「風が吹けば桶屋が儲かる」の典型だ。
- 日本人の使っている言語は、「遠い所にあるものは恐ろしい」というイメージスキーマを表象させている。その結果、日本の女性は子どもを産まない傾向になった。「未来」という「遠い所にいる自分、子ども」に不安を抱いているためだ。
- 日本人の中学生、高校生は、家で勉強しないという。「丸暗記中心」の受験中心の教育制度のためだ。これも「風が吹けば桶屋が儲かる」だ。
(正解…1,2,3です)。
◎事例・Ⅱ
A・虎穴(こけつ)に入らずんば虎子(こじ)を得ず
B・意味
思い切ってあえてリスクをとるという危険を冒(おか)さなければ、大きな成果は得られない、というたとえ。
虎の子を手に入れようとするならば恐ろしい虎のすむほら穴に入らなければいけない、といういわれからのたとえ。
C・設問
用例として適切なものはどれでしょうか。一つお選びください。
- 大不況になった。市場が蒸発した。それならば、第三次産業に投資しなければならないだろう。
- 世界は、長引く大不況になった。これまでの発想を変えなければならない。人材育成に投資すべきだ。
- 日本だけが、世界規模の大不況の中でダメージが大きい。若い世代に投資すべきだ。若い世代は、未来の象徴だからだ。
(正解…1,2,3です) |

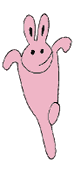





 「女性向け」、「男性の“女性”対応」のカウンセリング・ゼミです。
「女性向け」、「男性の“女性”対応」のカウンセリング・ゼミです。 女性と心を分かち合える「脳」を、最高に発達させる!!が教育の狙いと目的です。女性を「見る」「見たい」、女性から「見られる」「見られたい」関係をつくる、カウンセリング術です。
女性と心を分かち合える「脳」を、最高に発達させる!!が教育の狙いと目的です。女性を「見る」「見たい」、女性から「見られる」「見られたい」関係をつくる、カウンセリング術です。 女性の「脳を健康を働かせる」!安心と安らぎを分かち合う、が教育のテーマと目標です。「気持ちが安心する。だから、知的に考えられる」という女性の本質を支えつづけるカウンセリング術です。
女性の「脳を健康を働かせる」!安心と安らぎを分かち合う、が教育のテーマと目標です。「気持ちが安心する。だから、知的に考えられる」という女性の本質を支えつづけるカウンセリング術です。 女性の脳の働きが伸ばす「人格=パーソナリティ」を目ざましく発達させる!が教育の方針です。
女性が社会性の世界(学校・仕事・社会の規範・人間関係のルール・合理的な思考)と、知的に関われる!を一緒に考えつづけるカウンセリング術です。
女性の脳の働きが伸ばす「人格=パーソナリティ」を目ざましく発達させる!が教育の方針です。
女性が社会性の世界(学校・仕事・社会の規範・人間関係のルール・合理的な思考)と、知的に関われる!を一緒に考えつづけるカウンセリング術です。 ストレスを楽々のりこえる女性の「脳」を育てる!!が教育の人気の秘密です。女性は、脳の働きと五官覚の働き(察知して安心。共生して気持ちよくなる)とぴったりむすびついて、一生、発達しつづけます。
ストレスを楽々のりこえる女性の「脳」を育てる!!が教育の人気の秘密です。女性は、脳の働きと五官覚の働き(察知して安心。共生して気持ちよくなる)とぴったりむすびついて、一生、発達しつづけます。  人の性格(ものの考え方)が手に取るように分かる「心の観察学」
人の性格(ものの考え方)が手に取るように分かる「心の観察学」 心の病いに感染させられない「人間の関係学」がステキに身につきます。
心の病いに感染させられない「人間の関係学」がステキに身につきます。 心の病いを救出する、心と心をつなぐ「夢の架け橋術」
心の病いを救出する、心と心をつなぐ「夢の架け橋術」 相手に好かれる「対話術」がまぶしく輝くので、毎日が心の旅路。
相手に好かれる「対話術」がまぶしく輝くので、毎日が心の旅路。 相手の心の働きのつまづきが正しく分かって、「正しい心の地図をつくれる」ので、損失、リスクを防げます。
相手の心の働きのつまづきが正しく分かって、「正しい心の地図をつくれる」ので、損失、リスクを防げます。 学校に行くとイジメがこわいんです。私にも原因ありますか?
学校に行くとイジメがこわいんです。私にも原因ありますか?  怒りっぽいんです。反省しても、くりかえしています。治りますか?
怒りっぽいんです。反省しても、くりかえしています。治りますか?  「仕事・人生・組織に活かすカウンセリング」です。他者の心身のトラブルを解消できれば、自然に自分の心身のトラブルも解消します。
「仕事・人生・組織に活かすカウンセリング」です。他者の心身のトラブルを解消できれば、自然に自分の心身のトラブルも解消します。 プロ「教育者」向けのカウンセリング・ゼミです。
プロ「教育者」向けのカウンセリング・ゼミです。 「脳の健康を向上させる」、が教育のテーマと目標です。「指示性のカウンセリング」は、「考えたことを実行し、考えないことは実行しない」
という人間の本質を、最後まで励まし、勇気づけるカウンセリング術です。
「脳の健康を向上させる」、が教育のテーマと目標です。「指示性のカウンセリング」は、「考えたことを実行し、考えないことは実行しない」
という人間の本質を、最後まで励まし、勇気づけるカウンセリング術です。 脳の働きがつくる「人格=パーソナリティ」を育てる!が教育の方針です。
脳の働きがつくる「人格=パーソナリティ」を育てる!が教育の方針です。 ストレスに強い、元気に働く「脳」に成長させる!!が教育の魅力です。
ストレスに強い、元気に働く「脳」に成長させる!!が教育の魅力です。 「心の病いの診断学」が楽しく身につきます。
「心の病いの診断学」が楽しく身につきます。 心の病いの予防と解消の仕方の「人間の理解学」が身につきます。
心の病いの予防と解消の仕方の「人間の理解学」が身につきます。 心の病いに気づける「人間への愛情学」が驚くほど身につきます。
心の病いに気づける「人間への愛情学」が驚くほど身につきます。 「交渉術」の知性と対話の能力が目ざましく進化しつづけます。
「交渉術」の知性と対話の能力が目ざましく進化しつづけます。 相手の心の病理が分かって、正しく改善できるので心から喜ばれます。「心の診断術」
相手の心の病理が分かって、正しく改善できるので心から喜ばれます。「心の診断術」 病気になるということ、病気が治るということが正しく分かる、最高峰の知性が身につきます。
病気になるということ、病気が治るということが正しく分かる、最高峰の知性が身につきます。 朝、起きると無気力。仕事にヤル気が出ません。うつ病でしょうか?
朝、起きると無気力。仕事にヤル気が出ません。うつ病でしょうか?  仕事に行こうとおもうと、緊張して、どうしても行けません。治りますか?
仕事に行こうとおもうと、緊張して、どうしても行けません。治りますか? 






