| 「精神分裂病」の正しい理解の仕方 |
「精神分裂病」ということを精神医学として初めて真正面からとりあげたのは「E・ブロイラー」です。E・クレペリンは、分裂病を臨床的に観察して「早発性痴呆」という名称をつけて発表しました。E・クレペリンの書いた『早発性痴呆』(『破瓜病』昭和53年、星和書店・刊)の一部の要旨をご紹介すると、次のとおりです。
- 疾患は、通常、性的に発達する年齢に始まる。だから「思春期病」とも呼ぶ人もいる。
- 精神的作業力の低下が徐々に目立ってくるのが特徴だ。
たとえば、以前は品行方正でしかも優秀であった学生が、あっという間に挫折する。彼は、それまではなんでもなくこなしていた課題に耐えられなくなる。
とにかく、ノートを書く、文章を書くということができなくなる。
ぼんやりと日をすごして、おかしなミスやもっともらしいその場のがれの言い訳をするようになる。
- 患者は、仕事に行って収入を得るくらいの記憶力は保たれている。だが、人間関係の中である種の思考の貧困さが目立つようになる。説明する言葉の表象過程に因果のはっきりしないむすびつけ方が目立つ。あるいは、説明に欠落が多くなる。患者は、その説明の言葉を忘失しているのだ。
- 彼は、自分のこのおかしな状態にいくらか自覚的である。
自分は、努力が足りないのではないか?と自分を責める。あるいは、努力不足を改善すれば、自分の異常事態をなんとか切り抜けることができるのではないか?と独善的に考えるようだ。彼は、一日中机に向かってがむしゃらに暗記をしたり、夜になっても止めずにがんばったりする。
しかし、それで彼の精神活動力の低下が改善されるわけではない。
- 彼の生活の環境は秩序を保てなくなる。また、彼は、周囲の人に無関心になる。まわりの人の好意も悪意のひとつにとらえる。本をじっと見てもしかし、読んでいるわけではない。自分に課せられている義務を気にしなくなる。
|
| 分裂病は「弛緩」が本質 |
■E・クレペリンは、精神分裂病を「単純性痴呆」という描写から始めています。現実の社会的な活動や人間関係にたいして正常な関係や関わり方が崩壊する、ということが「痴呆」ということの観察の内容です。E・クレペリンの臨床の観察に見るように、「精神分裂病」は、客観的に見るかぎり、その人がもともともっていた「人物像」が一変して別のパーソナリティをあらわすといったものではありません。「痴呆」といわれている「状態」こそが「分裂病」の核心をなすものです。
「E・ブロイラー」は、E・クレペリンが記述したこの『早発性痴呆症』を分類して、整理しました。「E・ブロイラー」ののべるところの要旨を、再構成してご紹介します。
- 「精神病」というのは、思考や感情の「外界」にたいしての特異な変化のことだ。慢性化したり、病気の進行をくりかえしたり、病気の症状の段階にとどまったり、進行した症状が初めの症状に戻ったりするが、完全には元通りにはならないという症状群の全体を「精神分裂病」という名称で表現する。
- 精神分裂病を特徴づけるのは「連想活動」である。「連想すること自体」は、人間のもつ思考や表象の普遍的なものである。精神分裂病者のそれは「コンプレックス」から始まることが多い。コンプレックスは、健康人の場合は、一元的に合力して自分のもつ環境への働きかけ方の克服として独自の行動に集約する。だが、精神分裂病者のコンプレックスは社会的なパーソナリティを支配して、こうありたいという願望を作為的に表象する。その願望にリアリティを与えるために、そのための観念の活動がおこなわれる。これが連想活動となる。
(『早発性痴呆または精神分裂病の序論』医学書院・刊、昭和59年)
|
| 人間は緊張することが当り前 |
■E・ブロイラーはE・クレペリンの『早発性痴呆』を整理して分類しています。ブロイラーは、分裂病の症状をこまかく整理し、再構成して次のようにとらえました。
◎基礎症状
一次症状…「連想弛緩」(れんそうしかん)「感情の荒廃」
二次症状…「まわりの人との情緒的交流の喪失」「まわりの人の発言を拒否するか、攻撃する」「自閉」
◎副症状
「幻覚」「妄想」「錯乱」「緊張病症状」
■解説
E・ブロイラーの提唱した「精神分裂病」という名称を支持して、多くの門下生が集まりました。精神医学史の中でよく知られている精神医学者が門下生になっています。
E・ミンコフスキー、C・G・ユング、L・ビンスワンガーなどです。
E・ブロイラーの説明をみると、精神分裂病とは、「精神」が「弛緩・しかん」に「分裂することだ」ということがよく分かるでしょう。
「精神」とは「精神活動」の「精神」です。話すこと、聞くこと、読むこと、思考すること、身体を動かすことが「精神」です。
この「精神」は、呼吸を止めたり、心臓の心拍を低下させておこないます。すると身体の活動領域が「緊張する」でしょう。この「緊張」を「弛緩・しかん」させるというのが「分裂病」です。「弛緩・しかん」とは、輪ゴムを引っぱると緊張し、引っぱりを元に戻すと「ゆるむ」ということを思い浮べて理解できます。輪ゴムの引っぱりが「精神の緊張」です。輪ゴムの引っぱりをゆるめることが「弛緩・しかん」です。精神分裂病は、どういう意味でも「精神活動」をおこなうことを止めて、「弛緩・しかん」という「たるみ」や「ゆるみ」を求めて、「たるみ」や「ゆるみ」の心的な生活の中に安住することだけを合目的的に志向する、という病理です。 |
| 分裂病は連想がつくる |
E・ブロイラーは、分裂病の中心の症状の「弛緩・しかん」は「連想すること」でつくられるととらえました。ふつう、「妄想」を生じさせて、この妄想が「弛緩・しかん」の状態に陥らせる、と思われがちです。しかし「妄想」は、分裂病が進行した先の「社会的な人格・パーソナリティ」の統一性を失わせる特殊な「病理のイメージ」です。「A9神経」によって「幸福のボタン押し」といわれている「中隔核」からドーパミンを継続的に分泌させることを動機と目的にして表象されます。E・ブロイラーのいう「連想」は、「一つの考え」が思い浮び、この考えにつらなってとめどもなくつづいていく「思考によるイメージ」のことです。
分かりやすい例は、「過去のことを考える」とか「嫌なことを言われたので気になって、不快とか、怒りの感情とともに、気になっている言葉や人物のことを考えつづける」というものでしょう。
日本人は、「雨が降った」「ああ、驚いた」の助動詞『た』のように、過去のことか、現在もつづいている感情のことかがはっきりしない日本語(和語・やまとことば)で思考します。過去・現在・未来という時制を客観的に認識させないのが日本語です。(注・国語学者、大野晋の説明によります)。
すると、嬉しいことにつけても、不安なことにしても、過去のことを「現在の今の出来事」のように「連想して思い浮べる」ことが当り前におこなわれるでしょう。
「嬉しいことを思い浮べつづけて弛緩するというのは、実感としてもよく分かるが、しかし、不安なことや嫌なことを連想的に思い浮べて弛緩するということがよく分からない」と考える人もいるかもしれません。
E・ブロイラーの精神分裂病の定義の「基礎症状」に「自閉」という概念があります。「自閉」とは「弛緩・しかん」させる「イメージ」をくる日もくる日も固定的に継続することで、身体の五官覚(目、耳、皮ふ感覚など)の知覚機能を「マヒ状態」にさせることです。すると、人が話しかけたり、今、自分がかかわっている事柄に能動的に関わろうと思っても、放置状態になるでしょう。 |
| 分裂病は「離人症」が一貫する |
こういう心的な状態を「離人症」といいます。連想することのイメージが「嫌なこと」だったり「怒りに感じること」であると、そのイメージにたいしてアドレナリンが分泌して、心的には「対決する」とか「反論する」などといった身体の「活動状態」がつくられています。
スポーツや運動の「イメージトレーニング」というものがあります。頭の中で、自分がスポーツなり運動なりをおこなっている姿を継続的に思い浮べることです。「経験同一化の法則」といいます。「人間は、自分が考えたことを実行して、考えないことは実行しない」という法則のことです。「不安」や「怒り」の連想のイメージは、身体を経験同一化の状態に変えます。
すると、「人が楽しく話しかける」「急いで集中して仕事に取り組む」という現実にたいして正常に反応できないという離人症状態が生起します。
E・ブロイラーは、このような「離人症状態」を生起させるのが「連想」だとのべています。この「連想」に対応するのが「副症状」の「妄想」であったり「緊張病症状」です。そして「幻覚」や「錯乱」です。E・ブロイラー以降の精神医学者は、分裂病が、時代と社会によって変化するということに注目します。その変化は「妄想」「幻覚」「緊張病症」によってあらわされます。「妄想」によって時代と社会の変化が認められるということに注目した精神科医は「妄想主題」という言い方をしました。「妄想主題」とは、ある時代と社会では「神や悪魔」であったり、別の時代と社会では「無名の誰か」であったり、「ナチス・ドイツの時代と社会」では「ゲシュタポ」である、といったことです。
現代の精神医学は、E・ブロイラーが定義した「精神分裂病」の核心をなす「連想すること」が「弛緩・しかん」という分裂病の本態を生起するという説明を理解できないでいます。
それはなぜか?というと、「連想」とは、時代や社会、および個人の生育歴や家庭環境によって、たちまち病理の世界へ誘導する「言語的な不足」を表象するものだからです。 |
| 日本人は連想をおこないやすい |
先に、大野晋の日本語の説明をご紹介しました。
A・「雨が降った」
B・「ああ、驚いた」
の二つの事例です。
日本人は、日本語(和語・やまとことば)を弥生時代から用例の変化はあっても、文法型の基本構造はそのまま継承しています。このAとBの助動詞の『た』を「現在の出来事のことである」もしくは「これは、過去の出来事のことである」という時制の区別を明確にする人は、「過去の体験の連想」に「思考」が誘導されることはないでしょう。
しかし、生育歴の中で、親から「あんたは、いつだってこうなんだから」「あんたは、人のことはいろいろ言うけど、自分のことは棚にあげてすぐ文句を言う人だね」とか言われたことがある人は、「今のこと」と「過去のこと」を「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どのように」「どうした」という事実と事実関係の「名詞」や「助動詞」「助詞」の言葉に不適合を起こすでしょう。このような「日本語」(和語・やまとことば)への不適合が「弛緩・しかん」を生起する「連想」を思考させるのです。
現代の日本人の「連想」がつくる「弛緩・しかん」の分裂病のモデルの事例をご紹介します。 |
| 日本人のつくる「不適応」 |
《日本人の連想の仕方と分裂病の事例》
(島崎敏樹『精神分裂病における人格の自律性の意識の障碍』、『精神神経医学雑誌』精神神経学会・刊。昭和24年4月号、9月号より)
- こんなになったのは祖母のせいだ。祖母がいたからだ。祖母は、何かにつけて嫌味を言ったり、人のことを悪く言う人だった。
- 初めは、こちらが言うことが祖母はよく分からない。祖母が良いと思うことは、こちらがそうは思わない。こういう倫理の闘いのようなことがつづいた。
- そのうちに、こちらに弾力性がなくなってきた。祖母の性格がじわじわとこちらにのしかかってきた。初めは精神的なものだった。頭の中が二つに割れて、分かれて争っているような感じがした。本当の自分が表にある。しかし、裏には別のものがついている。この裏の別のものが感覚性をともなって悪の性格が外にも出るようになってきた。
- 祖母の性格が、自分の中に入ってきた。去年の秋頃だ。自分は乗っ取られた感じがした。
祖母の性格をもった顔が、頭の左側に30センチくらい離れて見え出した。人のことを悪意の眼で見る時は、祖母の性格をもった顔と眼がはっきりと見える。
- しばらくすると、祖母の性格の顔がいつもつきまとうようになった。
その顔は、パン粉のかたまりのような感触をもっている。黄色い色を感じる。それが私にとって第二の自我、悪の意思というべきものです。
■大野晋は『日本語練習帳』(岩波新書)の中で、「日本人にとっての人称代名詞」について説明しています。
- 日本語の敬語、人称代名詞は、相手あるいは、話題とする人やものごとが自分とどんな位置関係にあると扱うか、を示すものだ。相手を自分に、どんなふうに位置づけるか、扱い方の気配りや言葉づかいに表わすものだ。
- 相手が「自分の領域内にいる」と扱う時は、親愛や安心、時には侮蔑の扱いの表わし方になる。
大野晋の「日本語」(和語・やまとことば)の説明によると、日本人は、人間関係を「遠い」「中位の距離」「近い距離」の位置、空間でとらえていることが分かります。
言語社会学者の鈴木孝夫は、このことをとらえて、「日本人は、相手を意思ある主体とはみなさない」と説明します。日本人が「人称代名詞」と考えているものは、「げんみつにいうと、一人称、二人称というものは存在せず、しいていえばどの言い方も三人称とでもいうべきものだ」とのべています。
すると、この事例でのべられている「分裂病」では、どういう不適合が生起しているのでしょうか。
まず、「祖母」は、血縁関係でいうと最も遠い位置にいる存在です。血縁関係の権威といいます。事例の人物は、祖母にたいして「嫌悪」を示しています。これは、祖母の語るどんな言葉の「助詞」も、自分にとっては「不適応である」と受けとめられていることを意味しています。ちょうど、新しい職場に入って、いざ働こうと思うけれども、仕事の言葉が「どう行動していいか、なかなか記憶できないので、自分には合わない」と感じる場合と同じです。収入も、仕事の職種も納得がいって、たいへん「良い内容だ」とは思うが「行動にはつながらないので、自分には合わない、止める」と考える場合と同じです。これは、祖母との関係は「適応している」しかし「祖母の言葉とは不適合である」ということになるのです。日本人は、このように、「仕事」「勉強」には「適応している」(注・その場、その空間の中に自分を立たせて居つづけることができる、ということが適応です)、しかし、「相手の意思や言葉にたいして不適合である」という時に「分裂病」を生起します。 |
| 日本人の生活の中での分裂病のつくり方 |
日本人の「分裂病」の生起のさせ方は、したがって二重構造になっているというべきものです。「適応しているが、しかし不適合である」というパターンが現代版の分裂病です。このパターンを「境界型の分裂病」といいます。
もう一つは、「破瓜型(はかがた)の分裂病」です。これは、ある日突然、何の脈絡もなくパーソナリティとしての人格を崩壊させるというパターンの分裂病です。そのモデルとして吉本隆明の『共同幻想論』(巫女論)(角川ソフィア文庫)に、次のような「人格崩壊の分裂病」の説話が書かれています。要旨をご紹介します。
- 遠野という地域のあるところに、老女がいた。この老女は、特別の念仏の言葉を知っていた。その特別の念仏のまじないの言葉で蛇を殺したり、木にとまっている鳥を落したりする。だから、この老女の言うことは疑いなく本当のことだ。
- 老女はある話を聞かせてくれた。
「昔、あるところに、貧しい百姓がいてね」。
この百姓には妻がいない。死に別れたのだ。この百姓には、娘が一人いた。娘は、若くてきれいだった。
- 娘は、家にいた馬を愛した。愛したのだから夫婦になった。
- ある夜、父親はこれを知った。
父親は怒った。娘のいない時を見はからって馬を連れ出し、桑の木に吊り下げて殺した。
- 娘は、馬が殺されているのを見る。
死んだ馬の首にすがって、悲しくて泣く。
- 父親は娘が馬の首にすがりついているのを見て、馬が生きているもののように影響をもっていることを憎んだ。父親は馬の首を斧(おの)で切り落した。
- 娘は、馬の首に乗ってあっという間に天に昇っていった。
(『遠野物語』六九)
- 吉本隆明の説明(リライト再構成)
-
馬は、共同幻想を象徴する存在である。娘は、巫女(みこ)自身を重ねた人物のことである。
- こういう動物に象徴させられる共同幻想とは、家の中の三世代同居の中の「祖父母」と同じ位置関係をもつ。
「祖父母」は、血縁関係でいうと父や母よりも遠い位置にいる。距離の遠い存在だ。
その祖父母の語る言葉は、父親や母親の語る言葉よりも、自分の行動に直接の影響を及ぼさない。ちょうど学校の教師の語る言葉、知的な教育のための学習用テキストの中の言葉と同じだ。「意味」が分からなければ「行動しようがない」と見なされる。つねに遠くの位置から「なになにをせよ」「なになにをしてはいけない」と語りかけてくる。しかし「母親の語る言葉」のように自分の行動に安心感をもたらさない。「聞く」ことは可能で、「聞く」という適応の関係はつづくが、「言葉」とは「不適合」である。「語られる言葉の意味」が分からないので、せっかく「適応している関係」の行動が止まる。
- しかし、父親と母親は、祖父母を敬い、「権威」として認めている。「恐いもの」「自然のままに扱って、手を加えてはいけない存在」の象徴として扱っている。それは「ていねい語」や「敬語」「尊敬語」を用いて語りかけたり、関わっていることでよく分かる。だから、自分もそのように「遠くにいる存在」として関わるが、どうしても「敬語」「尊敬語」、「謙譲語」という言葉とその使い方が分からない。「家の中」という「自分の居場所」(安心できる場所)の中に「祖父母」が居るからだ。
- これは「日本語」(和語・やまとことば)のもつ「助詞」、「助動詞」がもっている「意味」にも規定されている。「行動をおこなう」という場合は「いつ」「どこで」「何を」「どのように」という行動の具体的な内容が「名詞のカテゴリー」で表現されなければならないが、日本語の助動詞の『た』は、つねに「行動が終わったもの」として表現させる。すると「祖父母」の語る言葉は「これからの行動のこと」であっても「すでに行動してしまった」かのように記憶される。
「やっていないではないか」と祖父母が言うと「もう行動は終了した」という意識が表象する。「やっていないではないか」と再び祖父母がくりかえして言い、説明を求めると、「祖父母との関係」の「不適合」を感じる。ここで「遠い位置にいる存在」の象徴としての「祖父母」は、「禁制を発する意思主体」に見える。
すると「適応の関係」(自分が家の中に居て安心の関係として関わること)の行動が止まる。「行動が止まる」ということは「人格を崩壊させる妄想の安心のイメージ」の中に逃亡するか、「自殺」に象徴される不幸な死の中に向かうしかない。
|
| 日本人の「人間関係」の中での不適合のしくみ |
■吉本隆明の『共同幻想論』の中には「憑人論」「巫女論」に加えて「巫覡(ふげき)論」(注・男性のシャーマンが巫覡(ふげき)。女性は巫女(みこ)と呼んだ。いずれも、神の言葉を人々に伝える役目をもつ人物のこと)があります。アジア型の共同幻想とは、村や国の人々が、間接的に、話し言葉で「禁制となる言葉」や「共同体の規範の言葉」を身体レベルの行動の言葉として記憶しなければならなかった原始社会の「観念」のことです。人間の観念は、「新生児」から「乳児」にかけて、五官覚の記憶する知覚を、右脳にイメージとして表象(ひょうしょう)するという「恒常性」のメカニズムのことです。この「五官覚の記憶」は、おもに「目」(視覚)と「耳」(聴覚)を中心とする知覚の記憶を「言葉」という記号として表象させます。これが言語の生成のしくみです。
大野晋は、『日本語の教室』(岩波新書)の中で次のように書いています。
- 文芸だけのことなら「漢文」を学ばなくてもいいかもしれない。漱石も鴎外も漢詩をつくっている。
このように「漢文」を習うということは、じつは文芸を学ぶのではなくて、最初から「倫理」や「論理」を教えられることだった。
- 私は、中学四年生の時、「幾何」が分からなくなった。やむなく「二年生の教科書」から学び直した。「平行線は交わらない」という公理から出発して「同位角は等しい」「二辺と夾角(きょうかく)の等しい三角形は合同である」と展開して、次々に定理を重ねていく一冊の教科書を復習し終えた。「ああ、学問とは、こんなふうに論理的な展開をしていくものをいうのだな」と思った。
- 『孟子(もうし)』を読んで「学問」と「議論」とは基本は同じことなのだと知った。これを「和歌」「和文」に求めても得られない。
- わずかに『枕草子』や『徒然草』に人生の智恵にわたる章があるにはあるが、趣味的な美意識の彫塑(ちょうそ)に寄っているように思われる。
つまり「思考の論理的展開」「人間性の洞察」については、日本人は「漢文」に頼って学んだ。
- 人間性の洞察ということになれば、和文として漱石が「好かない」と言っている『源氏物語』や近松の作品もある。『曽根崎心中(そねざきしんじゅう)』や『女殺油地獄(おんなごろしあぶらじごく)』などには、とめるにとめられない情熱にひかれて人倫に外れて、世間の義理との板ばさみになって死に至る人々の姿が描かれている。決して人間観察がゆるいとか甘いということはない。和文でそれを表現している。しかしそれらは劇であり物語であり、論述ではない。
つまり、日本人は漢文そのもの、その訓読系の文章によって明晰、簡明、論理的な組織化の重要性を学んだ。
|
| 日本人は新しく学ぶ局面で不適応になる |
■ここで大野晋がのべていることが「アジア型の共同幻想」の中心に存在する「意思」の内容です。「遠野物語」に出てくる人々の「観念」には、大野晋が説明する「漢文系の論理や論理の展開」という「意思」を中心とする「観念」がなかったのです。すると、「漢字」「漢文」によってつくられた「行動の仕方の説明の言葉」を「遠い所にあるもの、遠い位置にいる人間の意思」として区別するしかありません。
この「遠い所にある意思」の「遠い」とは必ずしも、物理的な距離だけをあらわすものではないことはよくお分りのとおりです。身近な空間の中にいることにも及ぼされます。このことを『遠野物語』はよく示しています。家の中のことであっても「何々をせよ」とか「何々をつづけよ」という遠い所に向かって進行していく「行動」の言葉にたいしても「遠さ」を感じています。
その「遠さ」の典型は「仕事」であり「言葉を学ぶこと」です。それは、『遠野物語』の共同体の世界にもあった、というエピソードを吉本隆明の『共同幻想論』の「巫女論」の中に見ていただきました。人間は、自分が初めて経験することや、状況や場面が変わる局面で「不適応を起こす」ということが象徴的に語られています。
『遠野物語』のエピソードは恋愛や結婚や、独立して家を出ること、などの局面で起こる「不適応」として見ることができるでしょう。ここで大野晋がのべている「日本語」(和語・やまとことば)の「文法」に規定されて「行動」が止まるか、無理に行動して過緊張状態に陥るでしょう。これが「分裂病」をつくる「不適合」です。日本人の分裂病は、「遠野物語」のエピソードに見るように、突然、社会的な人格が一変する「人格崩壊」を起こすパターンが原型になっています。それは、「父親が馬を殺す」「父親が、娘の悲しみに怒りを感じて、馬の首を斧で切り落す」といった行動のことです。今まで娘との関係は「適応関係」にあったのに、突然「自閉状態」に変わった、ということがのべられています。「自閉」とは、「怒り」にせよ「恐怖」にしろ、あるいは「快感を生成する美化のイメージ」であっても、その「イメージの維持と持続」に執着する行動のことをいいます。 |
| 不適応が強迫観念をつくるメカニズム |
なぜ、こういう「自閉」が生成されるのでしょうか。
島崎敏樹は『精神神経学雑誌』(精神神経学会・刊。昭和24年、4月号、9月号)で「精神分裂病における人格の自律性の意識の障碍(しょうがい)」の考察を次のように書いています。
- 離人症状態になるということに共通する傾向がある。
- 「何をしても自分がしているようではない。強いられて行動させられている気分になる」「自分は、機械になった気持ちになる。仕事をしても生き生きして感じられない」というものだ。
- 身体の知覚は、「自分が聞く」のではなくて「声が聞こえてくる」「声が聞こえる」というように、対象に即して体験させられるという知覚体験が表現される。
- 単に「声が聞こえてくる」場合でも「声が入ってくる」というように、「外の志向作用」として感覚的にとらえられる。
■これが「自閉」にともなう「離人症状態」の描写です。「離人症」は「遠野物語」の中にも出てきます。「不適応」の局面では必ず発生する「五官覚の遮断状態」が「離人症」であるからです。
大野晋は、『日本語の教室』(岩波新書)の中でこんなふうに書いています。
- ある時、中村真一郎から「君に言っておきたいことがある」と言われた。中村真一郎は、中学校のころからの付き合いだった。
「日本語で脚韻を踏んだ詩はできないと君は言っているらしいが、ヨーロッパでも詩人の努力で脚韻を踏めるようになったという事実がある」。
私は「困った」と思った。「日本語では脚韻は踏めない」とますます思っていたからだ。
- なぜ日本語では「脚韻を踏むソネットの制作」は困難か。
まず、日本語の文法形式がある。
ヨーロッパ語の文法構造は、「目的語となる名詞が文の終わりにくるのが正則」だ。単語の中で名詞がいちばん多い。
文末に名詞をおけると、安心していろいろな変化を作り出すことができる。
- だが、日本語は、名詞で文章を終わることは、原則としてできない。和歌に名詞止めの歌があるが、最後に「判断辞」がない。だから叙述としてイエスなのか、ノーなのかが分からない。名詞止めで終わるとは、日本語では「詠嘆」「感動」の対象として、その名詞を投げ出すしかない。
《事例》
心なき身にもあはれ知られけり鴫(しぎ)立つ沢の秋の夕暮
春過ぎて夏来るらし白妙の衣乾したり天の香具山
ソネットとは「14行詩」のことだ。ダンテの『新生』、ゲーテの『ファウスト』などがある。ボードレール、ヴェルレーヌ、ヴァレリーらが優れた作品をつくった。
ドイツのゲーテ、イギリスのシェイクスピアがソネットを定着させた。「脚韻」とは、文の終わりの言葉(名詞)を、音として美しく聞こえるように統一性をもたせることだ。
- 日本語の単語の6割は「名詞」だ。「動詞」の数はずっと少ない。日本語は、「動詞の終わり方」が決まっている。「歩く」「倒す」「来る」「噛む」のように必ず「母音」で終わる。
こまかく判断を示す場合は「動詞」の下に「だろう」や「ない」を付ける。だが、助動詞の数は合わせて30語にも満たない。日本語は、「文法的」には、「文」は「動詞」「助動詞」「助詞」で終わることに限られている。文末で形式的に変化がつけにくい。単調になる。
- 私は中村さんに言った。「日本語で脚韻を踏むことは、文法形式からも、音韻の上からも無理なのだと私は思うのです」。
中村さんは黙って私の話を聞いてくれた。中村さんは、それから二月あとに亡くなった。中村さんは病気だったのだ。
|
| 日本語の動詞は行動完結を意識させる |
■日本語(和語・やまとことば)の「動詞」は、「歩いた」「倒した」「噛んだ」「走った」などのように「行動が完結した表現」になる、ということは大野晋がのべているとおりです。「動詞」の数も少なくて、「判断」の言葉も限られるとのべています。「助動詞」の『た』は、「過去形」なのか「現在の感情の継続」なのかも分かりにくい、と説明します。
日本語のこのような『意味』の特性を分からずに、「仕事」や「勉強」にとりくむと、「日本語」そのものに「不適合」が生成するのです。すると、「仕事」の中で「自分の考えではない何かの考えが侵入してくる」という「自閉」が生じるのです。これは、ただ「行動のために仕事の言葉を憶える」という「仕事」や「勉強」の「適応」がつくり出します。
吉本隆明の『共同幻想論』の「遠野物語」には、結婚、恋愛、仕事、共同体の規範への参加といったことへの「適応」が「共同の意思」(漢字・漢語による秩序表現)との「不適合」を起こし、「一気に人格崩壊」を招くか、事故死に象徴される自殺(うつ病)に陥る、というエピソードが語られています。また、生活の中で行動のパターンが変わる局面では、今の現代ふうにいうと「境界型の分裂病」が生成する、というエピソードがのべられています。 |
| 不適合を防ぐための対策 |
現代の日本人の「境界型の分裂病」はなぜ起こるのでしょうか。それは、次のような「行動の方向性」が分からなくなっているからです。
◎助詞の「が」と「は」の使い方の法則
A・「が」の助詞の上には「疑問のこと」「未知のこと」「新しい発見を扱うこと」を据えて構文の主とする
B・「は」の助詞の上には、「話題としてすでに知っていること」「知られていると扱うこと」を据えて構文の主とする。「は」の上を「分かっているもの」と扱う。
(大野晋『日本語の教室』より)。
このような日本語の「文法の意味」を理解して、「同音類語」を書き言葉の中で「カテゴリー」の水準、距離、相互性として表現することが「日本型の分裂病」の「境界型の分裂病」「適応をもって社会と適合していると錯誤する自閉と離人症の生成」を防ぐ対策です。 |
| 不適応を防ぐ知性の学習モデル |
(注 A=B、B=C、故にA=Cという推移律(因果律)の学習モデルです)
■エクササイズ
◎事例・I
A・聞いて極楽見て地獄
(行動の仕方とその言葉に相当する。メタファーである。以下同じ)。
B・意味 (遠山啓の水道方式のタイルに相当する。推移律の基準になる。以下同じ)。
聞いたときは良く思えたが、実際に自分が見るとひどく悪いこと。
C・設問
分裂病の「不適合」を 防ぐことは、言葉の意味を正しく書いて説明できること、です。適切な用例はどれでしょうか?
用例
- テレビやケータイ、ゲームは面白いが、楽しさを良いことだと思いこんではまりこむ。
- 英会話を身につけるといいと言われて取り組んだが、人間関係の緊張が深まった。
- 文章の訓練をしようと思い、その日のことをノートに書いているが、いっこうにうまくならない。
(正解・1,2です)
|

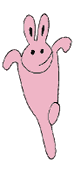




 「女性向け」、「男性の“女性”対応」のカウンセリング・ゼミです。
「女性向け」、「男性の“女性”対応」のカウンセリング・ゼミです。 女性と心を分かち合える「脳」を、最高に発達させる!!が教育の狙いと目的です。女性を「見る」「見たい」、女性から「見られる」「見られたい」関係をつくる、カウンセリング術です。
女性と心を分かち合える「脳」を、最高に発達させる!!が教育の狙いと目的です。女性を「見る」「見たい」、女性から「見られる」「見られたい」関係をつくる、カウンセリング術です。 女性の「脳を健康を働かせる」!安心と安らぎを分かち合う、が教育のテーマと目標です。「気持ちが安心する。だから、知的に考えられる」という女性の本質を支えつづけるカウンセリング術です。
女性の「脳を健康を働かせる」!安心と安らぎを分かち合う、が教育のテーマと目標です。「気持ちが安心する。だから、知的に考えられる」という女性の本質を支えつづけるカウンセリング術です。 女性の脳の働きが伸ばす「人格=パーソナリティ」を目ざましく発達させる!が教育の方針です。
女性が社会性の世界(学校・仕事・社会の規範・人間関係のルール・合理的な思考)と、知的に関われる!を一緒に考えつづけるカウンセリング術です。
女性の脳の働きが伸ばす「人格=パーソナリティ」を目ざましく発達させる!が教育の方針です。
女性が社会性の世界(学校・仕事・社会の規範・人間関係のルール・合理的な思考)と、知的に関われる!を一緒に考えつづけるカウンセリング術です。 ストレスを楽々のりこえる女性の「脳」を育てる!!が教育の人気の秘密です。女性は、脳の働きと五官覚の働き(察知して安心。共生して気持ちよくなる)とぴったりむすびついて、一生、発達しつづけます。
ストレスを楽々のりこえる女性の「脳」を育てる!!が教育の人気の秘密です。女性は、脳の働きと五官覚の働き(察知して安心。共生して気持ちよくなる)とぴったりむすびついて、一生、発達しつづけます。  人の性格(ものの考え方)が手に取るように分かる「心の観察学」
人の性格(ものの考え方)が手に取るように分かる「心の観察学」 心の病いに感染させられない「人間の関係学」がステキに身につきます。
心の病いに感染させられない「人間の関係学」がステキに身につきます。 心の病いを救出する、心と心をつなぐ「夢の架け橋術」
心の病いを救出する、心と心をつなぐ「夢の架け橋術」 相手に好かれる「対話術」がまぶしく輝くので、毎日が心の旅路。
相手に好かれる「対話術」がまぶしく輝くので、毎日が心の旅路。 相手の心の働きのつまづきが正しく分かって、「正しい心の地図をつくれる」ので、損失、リスクを防げます。
相手の心の働きのつまづきが正しく分かって、「正しい心の地図をつくれる」ので、損失、リスクを防げます。 学校に行くとイジメがこわいんです。私にも原因ありますか?
学校に行くとイジメがこわいんです。私にも原因ありますか?  怒りっぽいんです。反省しても、くりかえしています。治りますか?
怒りっぽいんです。反省しても、くりかえしています。治りますか?  「仕事・人生・組織に活かすカウンセリング」です。他者の心身のトラブルを解消できれば、自然に自分の心身のトラブルも解消します。
「仕事・人生・組織に活かすカウンセリング」です。他者の心身のトラブルを解消できれば、自然に自分の心身のトラブルも解消します。 プロ「教育者」向けのカウンセリング・ゼミです。
プロ「教育者」向けのカウンセリング・ゼミです。 「脳の健康を向上させる」、が教育のテーマと目標です。「指示性のカウンセリング」は、「考えたことを実行し、考えないことは実行しない」
という人間の本質を、最後まで励まし、勇気づけるカウンセリング術です。
「脳の健康を向上させる」、が教育のテーマと目標です。「指示性のカウンセリング」は、「考えたことを実行し、考えないことは実行しない」
という人間の本質を、最後まで励まし、勇気づけるカウンセリング術です。 脳の働きがつくる「人格=パーソナリティ」を育てる!が教育の方針です。
脳の働きがつくる「人格=パーソナリティ」を育てる!が教育の方針です。 ストレスに強い、元気に働く「脳」に成長させる!!が教育の魅力です。
ストレスに強い、元気に働く「脳」に成長させる!!が教育の魅力です。 「心の病いの診断学」が楽しく身につきます。
「心の病いの診断学」が楽しく身につきます。 心の病いの予防と解消の仕方の「人間の理解学」が身につきます。
心の病いの予防と解消の仕方の「人間の理解学」が身につきます。 心の病いに気づける「人間への愛情学」が驚くほど身につきます。
心の病いに気づける「人間への愛情学」が驚くほど身につきます。 「交渉術」の知性と対話の能力が目ざましく進化しつづけます。
「交渉術」の知性と対話の能力が目ざましく進化しつづけます。 相手の心の病理が分かって、正しく改善できるので心から喜ばれます。「心の診断術」
相手の心の病理が分かって、正しく改善できるので心から喜ばれます。「心の診断術」 病気になるということ、病気が治るということが正しく分かる、最高峰の知性が身につきます。
病気になるということ、病気が治るということが正しく分かる、最高峰の知性が身につきます。 朝、起きると無気力。仕事にヤル気が出ません。うつ病でしょうか?
朝、起きると無気力。仕事にヤル気が出ません。うつ病でしょうか?  仕事に行こうとおもうと、緊張して、どうしても行けません。治りますか?
仕事に行こうとおもうと、緊張して、どうしても行けません。治りますか? 






