| 「どのように」(Y経路系の言葉)という「説明の能力」が生き残れる時代になっています |
平成20年2月29日の日経に、小さな記事が載っていました。あらましは次のようなものです。
- 東京大学教授、薬理学の松本則夫らは、ラットの実験をおこなった。「嫌なことを思い出した直後にアルコールを飲むとその嫌な記憶が強められる」というものだ。
- 松本則夫教授らは、このことを米専門誌の「電子版」に発表した。
- 人間は、嫌なことを忘れようと酒を飲む。一時的に楽しくなっても、次の日は楽しいことを忘れて、嫌な記憶が残ることを、このラットの実験は示すものだという。
- 実験はこうだ。
カゴに入れたラットに電気ショックを与える。恐怖を学習させるのだ。ラットはカゴに入れただけで身をすくめて固くなる。この固まったラットにアルコールを注射する。アルコールを注射しないラットと比べた。アルコールを注射したラットは二週間固まりつづけた。このことにより「嫌なことの記憶が強くなった」と判断した。
- 結論はこうだ。
アルコールは記憶力を低下させるが、それは憶える段階でのことだ。いったん憶えたものを思い出して記憶に固定していく段階では、逆に、記憶を強める効果があるらしい、というものだ。
|
| 「どのように?」の論理実証の無い「デジタル表現」が「心理学」である
|
ここでは、「人間の脳」と「ラットの脳」は同じソフトウェアのメカニズムをもつ、ということが前提になっています。
「アメリカの専門誌」の「電子版」も、松本則夫教授らの実験とその考察を受け付けているので同じ見解であることが分かります。
また、「嫌なことの記憶」は、「ラットへの電気ショック」と「人間の場合の不快な記憶」と同一視されていることが分かります。人間にとって「電気ショック」に相当する「嫌な記憶」とは、身体に直接衝撃が与えられることを意味します。道を歩いていて自転車にぶつけられたとか、ぬれた手で電源コードのコンセントを触った、などのようなものです。
ここでは、明らかに、「人間にとっての嫌なことの記憶」の職場で不快なことを言われたとか、仕事にミスをして悔やんでいる、などと同じ次元で見ていることが分かります。
人間の脳は、大脳(左脳と右脳)をもつことで「下等哺乳類の脳」とは異なります。
人間にとっての「嫌な記憶」とは、「自分のミスで転んで脚を痛めた」という場合には「嫌な記憶」としては残りません。駅の階段で、意図的に押されて転んで脚を痛めた場合には、「なぜ、私だけが?」という思いとともに、いつまでも「不快な記憶」になって残るでしょう。これは、「右脳系の海馬」がエピソード記憶として記憶します。「嫌な記憶」は扁桃核と線状体でも記憶されると、「右脳のブローカー言語野の3分の1のゾーン」に表象(ひょうしょう)されるというように「思い出される」のです。
この「右脳に表象(ひょうしょう)される」というのは、ラットの実験の「カゴの中に入れられる」というように同一の状況に置かれたり、同一の環境におかれることが絶対条件ではありません。「行動が止まっている」か「半分だけ行動が止まっている」という条件があって初めて表象(ひょうしょう)されるものです。アルコールを飲んでいる時ならば、「逃げたい」「止めたい」「出来ない」などの「負の行動のイメージ」をつくる言葉を考えているか、もしくは、目の前の人と話していて「負の行動のイメージ」のための言葉がえんえんと話しつづけられる場合に「不快な記憶」が強まります。家では「左脳」は休息するので「負の行動のイメージ」が表象されつづけるでしょう。
これが人間にとっての「不快な記憶の強化のメカニズム」です。
もし、「負の行動のイメージ」をつくる言葉が思い出されなかったり、目の前の人と話すということがなければ、「不快なことの記憶」が思い出されることはありません。ラットには、「左脳、右脳という新皮質」はなく、「大脳辺縁系」だけで記憶しているので知覚系統がマヒして動けなくなったにしかすぎないという可能性もあります。
このように、「なぜそうなるのか?」の問いに答えて、発生から結果に至るまでのプロセスを解明して説明しないままに「アルコールの記憶に及ぼす障害作用の効果」まがいの療法を語る、という現象のモデルが松本則夫、東大教授の「実験」です。これと類似した実験を「心理学」の実験にも多く見ることができます。 |
ロルフ・デーゲンは、「心理学の実験」に依拠して、「心理療法」などの
「カウンセリング」について次のような批判を展開しています。
『フロイト先生のウソ』
(文春文庫、赤根洋子訳) |
- 人生という曲がりくねった道で迷子になったとき、心理カウンセラーに救いを求める人が増えている。「われわれは、心理療法と自己改造の時代に生きている」とアメリカの社会心理学者マーティン・ゼーリヒアンはのべる。「彼らは、心理学の専門家の指導を受ければ、人格は根本から変えられる、性格的な短所や欠点を直すことができる、と信じ込んでいる」。
100年前にフロイトが精神分析を発明して以来、心理療法は先進諸国にあまねく広がり、冒すべからざる真理としての地位を確立するに至った。心理療法の「供給者」は「健康保険制度の充実したわが国(ドイツ)においては、どんな精神障害に対しても専門的な治療法がある」という根拠のない希望的観測を抱かせる。
- 「最近では、心理療法は多くの人にとって宗教の代用品と化してしまった」(スイスの社会精神医学者、アムスム・フィンツェン)。
「彼らにとって、心理療法は、ルルドの泉と同じようなものなのだろう。彼らは、心理療法に奇蹟を期待しているのだ」。
しかし、こうした過大な期待は科学的認識からかけ離れている。
数十年間に及ぶ「実証的データにもとづく心理療法研究」の結果、明らかになったのは「心理療法は、精神障害にたいして恐ろしいほど、おそらくは完全に、無力であるだけではなく、最悪の場合には治療するどころか、精神障害を引き起こす場合さえある」という事実だった。
1997年に死去したイギリスの心理学者ハンス・コルゲン・アイゼンク(心理療法の批判の世界的な心理学者)は、何十年も前にこのような全面否定の否定的結論に達していた。
- カウンセリングの有効性を原則的に認めている人々でさえ、実際の利用価値については否定的である。アメリカの心理学者テレンス・W・キャンベルの意見。
「30年以上にわたって研究をつづけてきたが、膨大なデータから引き出せる結論は次の一点に尽きる。心理療法によって良くなる人もいるが、かえって悪くなる場合も多い。多くの症例について調査すると、この相反する効果が相殺されて、差し引きゼロとなる」。
ドイツの科学ジャーナリスト、ディーター・E・ツィンマーも同意見だ。
「現在おこなわれている心理療法の理論上の基礎は、そのほとんどが科学的に見て、疑わしい。全くのインチキ療法と言わざるを得ないものもある」。
- 最近、「セラピスト」の「似非専門知識」にたいする識者の批判が相次いでいる。
イギリスの精神科医ガース・ウッドの発言。
「セラピストは他人の心の中を見通すことができる、現在の心理状態どころかその人の未来までも予言できるかもしれない、と一般的に信じられている。実際には、もちろん、そんなはずはない」。
「心理療法という神話の作り手たちは、病んだ精神も、破裂した水道管や故障した自動車と同じように、専門技能によって治せる、とわれわれに信じ込ませようとしてきた。まったくナンセンスな話だ。実際には、こうしたセラピストたちは、有意義な訓練を受けてもいないし、特別なスキルを身につけているわけでもない。こんなにも長い間、人を騙してこられたとは奇蹟である」。
- 心理学の古典的な得意分野は、問いかけをおこなうことだった。例えば、「ノイローゼの原因は何か?」などだ。
しかし、心理療法はとうの昔に悟っている。問いかけでは儲からない。儲けるには答えを与えることだ、と。
しかし、正しい答えの持ち合わせはない。そこで、答えを欲しがる人にはありきたりのい決り文句と神話を与えてお茶を濁すというわけである。かつての謙虚な好奇心は、今や傲慢な確信に取って代わられてしまった。
「心理学産業は人々にだぼらを売りつけている。心理療法は多くの点でペテンに過ぎない。心理療法は現代のガマの油だ」(ダイニーン)。
だぼらを売って儲けようという専門家は増えつづけている。業界は、市場と顧客層の拡大を図る必要に迫られている。この目的を達成するには、日常の些細なことに無理にでも病名をつけるしかない。ただの疲れが「慢性疲労症候群」となり、辛い思い出は「心的外傷後ストレス障害」(PTSD)と呼ばれるのだ。
ついには、ちょっとでも心に不調があれば専門家のもとにおもむいてクライアントになりなさい、ということになる。
- 心理療法は、一般社会から期待されていて、しかも福祉に手厚い国家からはたっぷりと補助金を受け取って、成長産業となった。現在、ドイツには、大学で専門教育を受けた臨床心理士がざっと一万四○○○人もいる。臨床心理士を目指していて心理学を学ぶ学生は三万人もいる。フロイトが精神分析という「無意識へ至る道」を発見して以来、600種類以上もの心理療法が生まれた。それぞれ効能(荒唐無稽(こうとうむけい)なものもなる)を掲げてクライアントを奪い合っている。分派だの異端だのが増殖していく速さにはどんな百科事典も追いつかない。心理療法というジャングルの入り組み具合に比べれば、中東のバザールも整然としているように見える。
マーティン・ゼーリヒマンはこうのべる。
「心理療法の実際の効果について批判すべきときがきている。人間は、そうそう変えられるものではない。最近分かったことだが、われわれの人格…知性や音楽才能はもちろん、信心深さ、良心(もしくは良心の無さ)、政治的信条、気質に至るまで、のかなりの部分を決定しているのは遺伝子なのである」。
これまでのところ、セラピストたちは、このような宿命論的な謙虚さとは無縁である。
|
| 「心理療法」および「心理学」とはどういうものか |
ここで、ロルフ・デーゲンが批判している「心理療法」について解説をおこないます。ネットで一般的に流通している「心理療法」について「フリー百科事典、ウィキペディア」から要点をご紹介します。
- 心理療法とは、精神疾患の治療、心理的問題の解決、あるいは精神的健康の増進を目的とする理論、技法の体系のことだ。
- 「臨床心理学」の分野では心理療法と呼ばれる。精神医学の分野では精神療法と呼ばれる。実際には同じものを指している。
心理療法をおこなう人は、カウンセラー、セラピスト、治療者と呼ばれる。
心理療法を受ける人は「クライアント」「患者」などと呼ばれる。
心理療法として「エネルギー療法」「眼球運動による脱感作」がある。
- おもな「心理療法」は「精神分析」「力動的心理学、深層心理学」「行動療法」「イメージ療法」「認知療法」「集団療法」「家族療法」「カップル・セラピー」「遊戯療法」「箱庭療法」「ゲシュタルト療法」「森田療法」「内観療法」「自律訓練法」「催眠療法」「回想法」などがある。
- 「クライアント」の意味は、次のようなものである。
広告の場面で「依頼人、顧客」。
心理療法で「カウンセリングを受ける人。社会福祉の援助を受ける人」。
コンピュータ業界で「サーバからのサービスの依頼をおこない、その提供を受ける人」。
- 「精神分析」とは次のような主旨のことである。
ジクムント・フロイトによって創始された。人間心理の理論と治療技法の体系を指す。広義には、「フロイト以降」の分派を含めた理論体系の全体も指している。
向精神薬の「クロルプロマジン」の再発見以来、精神疾患への薬物療法が発達した。1980年の「DSM‐Ⅳ」(精神疾患の診断と統計の手引き・アメリカ)の発表以降、「神経症」の概念が解体される方向に向かった。だが、「精神医学」が「薬物療法」「生物学的理論」に偏りすぎたことへの反動が起こる。「摂食障害」「人格障害」などは、薬物療法のみでは治療が困難となり、「精神分析」の一つの「認知行動療法」が適用されつつある。
- フロイトの考えとは次のようなものである。
人間には「無意識の過程」がある。人の行動は「無意識」によって左右されるというのが基本的な仮説である。人は、意識することが苦痛であるような「欲望」を無意識に抑圧することがあるととらえる。この抑圧が姿を変えて、「神経症」などの症状をあらわす、というものである。そこで、「無意識の領域」に「抑圧」されている葛藤などの内容を自覚させることで症状が治る、という治療の仮説を立てた、と考えられている。
「フロイト」以降の分派は次のとおりである。「古典フロイト派」「自我心理学」「新フロイト派」「自己心理学」などだ。
「臨床療法」としてのフロイトの精神分析は、医学の世界では幅広い支持を得ているとはいえない。だが、思想としての精神分析の理論は、「人間理解」「人文諸学」「心理学」に影響力をもっている。世相の観察、芸術作品、犯罪などのいろいろな事象の理解、批評に援用されている。
ミシェル・フーコーは、精神分析を「リベラル・アート」(一般教養)のようなものだと主張している。
- 「心理学」とは何か。一般に、「心」と呼ばれるもののさまざまな「働き」である「心的な過程」とこれにもとづく「行動」を探求する学問、とされる。
「科学的経験主義の立場」から観察、実験によって探求をおしすすめようとする「実験心理学」、精神に不調をきたした人の理解、および援助を指向する「臨床心理学」、心を脳という情報処理装置と解釈する「認知心理学」、人文科学・哲学からアプローチする「人間性心理学」などの立場がある、とされる。
独立した「科学分野」としての「心理学」は、感覚、知覚などの「低次な機能」を扱う「知覚心理学」と、記憶や言語など「高次の機能」を扱う「認知心理学」に大別される、といわれている。
- 「生理学から発展した心理学」。
脳を損傷すると精神機能に異変が生じる。このことから「脳が感情や思考などの精神現象を生み出す中枢」であるとみなして、「脳を構成する神経系を調べることで精神現象を解明できる可能性がある」との立場が生まれた。
この発想自体は、古くは、デカルトが「心身合一の問題」として言及しているが、実験的に調べられるようになったのは19世紀以降である。
- 19世紀の「ブローカー」や「ウェルニッケ」らの失語症と脳損傷の関係調査により「言語中枢」とされる「脳部位と言語野」が推定された。この研究により「言語」を扱う精神機能が、「脳」という生理的土台によって生じることが明らかになった。
「脳損傷」と「精神機能の失調」との関係調査は、20世紀の初頭の第一次大戦以降、戦争で「脳」を損傷した患者の治療過程で大きく進んだ。1960年代からは「CT」により「脳血管障害患者の脳」を非侵襲的に調べられるようになり、さらに進展した。
|
| 「心理療法のカウンセリング」と「ポルソナーレのカウンセリング」は、何が、どう違うのか
|
「心理学」や「心理療法」について、一般的にはどのように理解されているかの「解説」をご紹介しました。
「心理学」と「心理療法」は、もともとはフロイトが創始したもので、ここからいくつもの分派が派生して、ドイツでは「学」と「療法」が500以上もあるといわれています。
フロイトが解明した人間についての理解のための「概念」のおもなものは「無意識」「自覚的な意識」「記憶」「回避」「抑圧」「症状」といったものです。
「心理学」や「心理療法」は、「無意識」「意識」に対応する「行動」を考察の対象とはせず、無意識と自覚的な意識に対応しない「行動パターン」を「認知」したり、もしくは「認識」できた現象を「治療する」ということをおこなっていることが分かります。
心理学の「認知」の仕方は「動物実験」であったり「アンケートによる調査」であったり、テーマを決めた「人間行動の観察」のことです。
統計学的な手法や、偶然の要素は介入していないと測定される事実や事実関係が「認知される科学である」と公認されています。心理学の「認識の仕方」とはどういうものでしょうか。観察される人間の「ものの考え方」を形成する「無意識」や「自覚的な意識」は考察の対象にされていないことはすでにお分りのとおりです。
「この人はこう思ったに違いない」「この人は、このような思考パターンをもっているに違いない」といった「解釈」を加えて定義したものが心理学の「認識」です。
「心理学」とは何か?といえば「行動パターン」をどこまでも拡大して観察し、これにたいしてその都度「解釈」を加えることを「科学」とする学問であるといえます。
では、ポルソナーレの「カウンセリング」とは、どこがどう違うのでしょうか。
ポルソナーレのカウンセリングは、「社会教育法としてのカウンセリング」です。
人間の行動を「社会」(共同性の観念ともいいます)の中で適合、もしくは適応しつづける状態をモデルとして想定し、不適合や不適応の行動の事実を「病理である」と定義します。「行動」の支障や障害、もしくは、停止が「病理」です。「社会教育法としてのカウンセリング」をになうポルソナーレの知的な対象とテーマは、三つです。一つは、万人に共通する「社会性とは何か?」、二つ目は「現在と未来にかかわる社会の共同意思とはどういうものか?」(経済や政治の動向と、教育や医療の変遷(へんせん)など)、「人間の一人一人に共通する不適応と不適合の思考のメカニズム」が三つ目です。
ポルソナーレの「社会教育法としてのカウンセリング」と「心理学、心理療法」「DSM」「精神分析」のとらえる「病理」についての理解の違いとは、こうです。
ポルソナーレの「病理」についての見解……「あらかじめトラブルを予測して、そのトラブルの解決の方法を分かることが健康である。したがって、問題の解決の方法が分かっていれば、症状があっても、疾患があっても病気とはいえない」。
「DSM」など心理療法の「病理」についての見解……「特定の症状が2週間とか2ヵ月とかの期間つづいていれば、その症状によって表現される支障や障害の行動パターンのとおりの病気である」。
ロルフ・デーゲンの「心理療法」への批判の仕方は、いわば「反措定」(はんそてい)というべきものです。
措定(そてい)とは哲学の概念ですが、「ものごとの内容が、言われているような内容と必ずしも一致しないではないか」というような批判の仕方です。
「うちには犬がいる。この子は、家族の一員だ」といった発言にたいして、「じゃあ、その犬は義理の関係か?それとも直接の血縁関係なのか?」と問いかけることが反措定(はんそてい)です。「あなたは、一緒に暮らして、気持ちの孤独感をなくしてくれる生き物を家族と規定しているのだ」という発言が「措定」(そてい)です。ロルフ・デーゲンの「心理療法」の批判の具体例をご紹介します。 |
| ロルフ・デーゲンの「子どもの家庭教育」批判 |
- 教育の圧倒的な力にたいする信仰の起源は、精神分析の祖ジークムント・フロイトである。彼のトラウマ理論によれば、人生を決定づける最も重要な時期は最初の6年間だという。幼児期の精神的苦痛、つまりいわゆるトラウマは成長過程の中で克服されずに「無意識」の中に残り、一生のあいだ心身に悪影響を及ぼすのだという。サイコセラピストにとっては、患者の夢や自由連想の中に幼児期の抑圧された精神的打撃の暗示が見出せれば、それだけで充分な証拠となる。
発達心理学の権威、ハーバード大学のジェローム・ケーガンはいう。
「南京大虐殺、文化大革命、ボスニアの、ルアンダの大量虐殺……こうした残虐行為をおこなった男たちの大部分は、両親の愛情に包まれて育ったに違いない。
なぜかといえば、ヘミンガーの追跡調査によれば、豊かな才能と愛情深い円満な人たちの中に、トラウマティックな家庭環境で子ども時代を送った人が、驚くほどの高率で見られたからだ。
また、何の問題もない恵まれた環境に育った才能豊かな子どもが、成長後、フラストレーションや神経症を抱えていることが分かった」。
- 恵まれない家庭や施設から里親に引き取られた子どもは、転換の激動期を経て日常的な家庭生活になじんでいく。
妊娠中(本人の誕生前)の複雑な事情も、彼らの最終的な社会適応能力にとって何らハンディキャップとはならない。家庭の愛情を知らずに施設で数年間を過した子どもでさえ驚くほど短期間に新しい環境に順応する。
- 生後七ヵ月以前に、施設に引き取られた子ども137人について調査がおこなわれた。ふつうの家庭に育った子どもと比較するといくらか「人見知りする」傾向が見られた。しかし、攻撃性、非行、知的発達の遅れ、反社会性といった特徴に関しては何らの違いも観られなかった。(フンボルト大学心理学研究所、イェンヌ・アーゼンドルプフ教授)。
- ロルフ・デーゲンのこの「子どもの頃の親子関係や家庭環境」と、「子どもの成長後の比較の調査」は、どのように説明されるものなのでしょうか。
「心理学」の学的な方法は、人間の無意識や自覚的な意識は観察の対象としないことは、すでにご説明しているとおりです。「行動パターン」の事実について調べて観察し、これを「認知」します。この「認知した事実」について「攻撃性は?」「非行は?」「知的な遅れは?」と問い、「認識」します。
本人の「ものの考え方」「気持ちに感じられている安定、不安定」「無意識」とは無関係に「解釈」するのです。しかし、人間の全ての病理は、「行動停止」か「半行動停止」の状態の時に、「右脳」に、「負の行動のイメージ」として表象されます。
したがって、調査は、「本人のものの考え方」に「社会との適応性があるか?どうか?」が前提におかれなければなりません。
ロルフ・デーゲンは、「反措定」の問いとして、このように科学的な論理実証としての回答があるか、どうかを「心理療法」に問いかけているのです。 |
| 乳児の脳の「言葉の生成」のメカニズム |
「乳児」(生後6ヵ月から8ヵ月)の「社会への適応」の能力は、「言葉」の生成から始まります。無藤隆は、『赤ん坊から見た世界・言語以前の光景』(講談社現代新書)の中で、次のような観察を紹介しています。
- ここに一つの研究がある。二つのグループの母子の研究である。一つは「家庭で養育されている子ども」のグループ、もう一つは「母親が外で働き、保育所に子どもを預けているグループ」だ。
この調査のテーマは、子どもが物の名称をどれくらいの早さと量を憶えるか?というものである。
- 「子どもが目で見て注視している物」について母親がその物の名称を話すという時の「発語」を「現在母親発話」という。
二つの子どものグループの、「現在母親発話」の少ない「外で働く母親の子ども」は、「一年後に、どのような語彙(ごい。一定の範囲で用いられる語の総体を集めたもののこと)を獲得しているか?予測できない。
一方、「家庭内で養育されているグループ」は、「現在母親発話」と「乳児自身の音声的模倣」の両方で、一年後の語彙(ごい)の獲得が、統計的に意味のある関連の大きさに達していた。
乳児の「言葉の獲得」は、母親の言葉のかけ方、とくに「現在母親発話」が重要であることを示している。
- 奈良女子大学の麻生武の説明。
- 生後9ヵ月の子どもが、天井からぶら下げた「おもちゃのうさぎ」のスイッチをオンにして「うさぎ」が動くと子どもは泣き止む。うさぎは、声を出し、こんにちは、とおじぎをする。
- 母親が子どもを抱き、うさぎに近づけると子どもは、笑う。子どもをうさぎから1メートル離すと、子どもは、左手をうさぎの方に伸ばした。人差し指と親指で、うさぎをつかもうとする形である。
- 子どもを、うさぎから2メートル離す。乳児は、左手をうさぎの方にさらに伸ばす。体もうさぎの方に乗り出す形になる。うさぎの方に近づかないと、泣き顔になり、機嫌が悪くなる。
- そこで、乳児をうさぎに近づけて、手が届く距離にまで近づく。乳児は、左手を下す。手で触れようとはしない。また、2メートルほど離れると左手を伸ばす。移動しないと機嫌が悪くなり、うさぎに近づくと、手を下す。
- 乳児は、生後6ヵ月くらいから母親が、指で物を指さすと、その指の先の方向を見る、ということをおこなう。興味深いものがあれば、その物をじっと見る。
物が何もないときは、視線を戻して、母親の顔をじっと見る。
|
| 「視覚のクローズ・アップ」が「聴覚の記憶」になり「言葉」になる |
0歳6ヵ月から1歳児の乳児の脳は、どのように「言葉」をつくり出すのか?が観察されている事例です。
ここでは、乳児の「手を伸ばす」「指をさす」という行動が注目されています。この「指をさす」ことが脳が「言葉を生成している」ことのメカニズムを象徴しています。乳児の脳の「言葉の生成」には、母親の「言葉がけ」が条件になっていると観察されています。
では、脳のソフトウェアとしてのメカニズムから見ると、乳児の脳はどのように「言葉」を生み出すのでしょうか。
まず、乳児の脳を「左脳」と「右脳」とに分けてとらえることが必要です。言葉は、「左脳」で記憶されるからです。
「天井からつるしたうさぎのおもちゃ」への乳児の関わり方の実験例をとりあげてみましょう。
遠くの位置から「うさぎ」を見ています。「見る」というのは「視覚」です。乳児は、「うさぎの動き」に目をとめて、次に、じっとうさぎを注視する、と観察されています。これは、「右脳」のブローカー言語野の3分の2のゾーンで「Y経路」による「動きのパターン認知」が記憶されて、次に、「動くもの」だけに焦点が合わされています。「うさぎ」が認識されているのです。視覚の「X経路」によって記憶されています。右脳のブローカー言語野の「3分の1」のゾーンで「クローズ・アップ」のイメージが表象されます。
ところで、この「クローズ・アップ」は「ウェルニッケ言語野の触覚の認知」と相互性をもった記憶の仕方になります。クローズ・アップと触覚の認知は同義であるというメカニズムについてはすでにご説明しているとおりです。ところで、視覚の認識「X経路」がクローズ・アップの表象になるということは、同時に、「聴覚の認識」としても記憶されるということと同じメカニズムになるのです。「聴覚の経路」と「視覚の経路」は、脳の中で同じ「経路」をとおっています。視覚の情報は「外側膝状体」で視覚の記憶細胞へ送られ、聴覚の情報は、「内側膝状体」で聴覚野の細胞に記憶されるというシステムになっています。このシステムについてもすでにお話しています。
胎内にいる時の胎児は、「視覚」よりも「聴覚」の機能が先行して発達しています。母親の心臓の拍動を「X経路・左脳で聴く」、母親の動脈の血液の流れの音を「Y経路・右脳」で聴く、というように、左脳と右脳の「聴覚野」の機能を発達させてきています。
ところで、「左脳」の「聴覚」という知覚がとらえる認識の内容とは何でしょうか。
それは、「視覚のクローズ・アップしたイメージ」が、よりいっそう「クローズ・アップ」されて「シンボリックな形象」として表象されることがその内容です。これは、「自然の音」と、人間の声の「人工的な音」とを比べてみるとよく理解されるでしょう。自然の音は形象的なイメージを表象しません。「心臓の心拍」を中心にした「安心」と「不安、もしくは緊張」を「右脳系の大脳辺縁系の線状体」から「右脳」のブローカー言語野に表象させます。人間の声の「人工的な音」は、「象形文字」や「楔形(せっけい)文字」に見られるように「シンボリックな形象」を「右脳・ブローカー3分の1のゾーン」に表象させるのです。
音の長さや短さ、強さや弱さという「知覚的な認知」が、「音節の音声」という記号性と対応しています。これが「左脳」で「記号として認識される」(長期記憶)時に「言葉」になるのです。
みなさんは、鳥や動物がキーキ、とか、ピーピーとかの「声」を出して群をつくったり、仲間どうしが集まっている光景を見ることがおありでしょう。これは、「脳」の「大脳辺縁系」と「小脳」の中枢の「触覚の認知」を「聴覚」や「視覚」に表象させた「交信」がおこなわれているのです。「人間の言葉」は「左脳」での記憶ですが、「人間」が、風や雨、虫の音などの音を聴く「右脳系の聴覚」と同じです。人間の乳児は、母親の声を右脳で聴き、視覚のY経路を「X経路」で認識して母親の顔をクローズ・アップさせて「母親」を触覚的に認知します。この母親の顔の「クローズ・アップ」が「シンボリックな形象」まで抽象化して「記号性」をおびます。この「記号性の形象」が「左脳」で記憶されます。すると視覚的に内包されている「触覚的な認知」の長期記憶は「母親という対象と自分とはむすびついている」という「関係意識」に変わるのです。この記号性の形象がつくり出す「関係意識」にもとづいて、乳児が「物」(うさぎ)に近づくと、「うさぎ」という「実物のイメージ」が、記号性の形象のイメージに重なったクローズ・アップとして表象し、A10神経によりドーパミンが分泌します。この「クローズ・アップの表象」に、「シンボリックな形象」の記号性を「発生の長さや、強弱などの記号性」で表現したものが、内包する「音節」です。この「音節」の表現とクローズアップのイメージの表象が「言葉」であるのです。 |

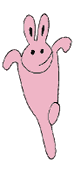


 「女性向け」、「男性の“女性”対応」のカウンセリング・ゼミです。
「女性向け」、「男性の“女性”対応」のカウンセリング・ゼミです。 女性と心を分かち合える「脳」を、最高に発達させる!!が教育の狙いと目的です。女性を「見る」「見たい」、女性から「見られる」「見られたい」関係をつくる、カウンセリング術です。
女性と心を分かち合える「脳」を、最高に発達させる!!が教育の狙いと目的です。女性を「見る」「見たい」、女性から「見られる」「見られたい」関係をつくる、カウンセリング術です。 女性の「脳を健康を働かせる」!安心と安らぎを分かち合う、が教育のテーマと目標です。「気持ちが安心する。だから、知的に考えられる」という女性の本質を支えつづけるカウンセリング術です。
女性の「脳を健康を働かせる」!安心と安らぎを分かち合う、が教育のテーマと目標です。「気持ちが安心する。だから、知的に考えられる」という女性の本質を支えつづけるカウンセリング術です。 女性の脳の働きが伸ばす「人格=パーソナリティ」を目ざましく発達させる!が教育の方針です。
女性が社会性の世界(学校・仕事・社会の規範・人間関係のルール・合理的な思考)と、知的に関われる!を一緒に考えつづけるカウンセリング術です。
女性の脳の働きが伸ばす「人格=パーソナリティ」を目ざましく発達させる!が教育の方針です。
女性が社会性の世界(学校・仕事・社会の規範・人間関係のルール・合理的な思考)と、知的に関われる!を一緒に考えつづけるカウンセリング術です。 ストレスを楽々のりこえる女性の「脳」を育てる!!が教育の人気の秘密です。女性は、脳の働きと五官覚の働き(察知して安心。共生して気持ちよくなる)とぴったりむすびついて、一生、発達しつづけます。
ストレスを楽々のりこえる女性の「脳」を育てる!!が教育の人気の秘密です。女性は、脳の働きと五官覚の働き(察知して安心。共生して気持ちよくなる)とぴったりむすびついて、一生、発達しつづけます。  人の性格(ものの考え方)が手に取るように分かる「心の観察学」
人の性格(ものの考え方)が手に取るように分かる「心の観察学」 心の病いに感染させられない「人間の関係学」がステキに身につきます。
心の病いに感染させられない「人間の関係学」がステキに身につきます。 心の病いを救出する、心と心をつなぐ「夢の架け橋術」
心の病いを救出する、心と心をつなぐ「夢の架け橋術」 相手に好かれる「対話術」がまぶしく輝くので、毎日が心の旅路。
相手に好かれる「対話術」がまぶしく輝くので、毎日が心の旅路。 相手の心の働きのつまづきが正しく分かって、「正しい心の地図をつくれる」ので、損失、リスクを防げます。
相手の心の働きのつまづきが正しく分かって、「正しい心の地図をつくれる」ので、損失、リスクを防げます。 学校に行くとイジメがこわいんです。私にも原因ありますか?
学校に行くとイジメがこわいんです。私にも原因ありますか?  怒りっぽいんです。反省しても、くりかえしています。治りますか?
怒りっぽいんです。反省しても、くりかえしています。治りますか?  「仕事・人生・組織に活かすカウンセリング」です。他者の心身のトラブルを解消できれば、自然に自分の心身のトラブルも解消します。
「仕事・人生・組織に活かすカウンセリング」です。他者の心身のトラブルを解消できれば、自然に自分の心身のトラブルも解消します。 プロ「教育者」向けのカウンセリング・ゼミです。
プロ「教育者」向けのカウンセリング・ゼミです。 「脳の健康を向上させる」、が教育のテーマと目標です。「指示性のカウンセリング」は、「考えたことを実行し、考えないことは実行しない」
という人間の本質を、最後まで励まし、勇気づけるカウンセリング術です。
「脳の健康を向上させる」、が教育のテーマと目標です。「指示性のカウンセリング」は、「考えたことを実行し、考えないことは実行しない」
という人間の本質を、最後まで励まし、勇気づけるカウンセリング術です。 脳の働きがつくる「人格=パーソナリティ」を育てる!が教育の方針です。
脳の働きがつくる「人格=パーソナリティ」を育てる!が教育の方針です。 ストレスに強い、元気に働く「脳」に成長させる!!が教育の魅力です。
ストレスに強い、元気に働く「脳」に成長させる!!が教育の魅力です。 「心の病いの診断学」が楽しく身につきます。
「心の病いの診断学」が楽しく身につきます。 心の病いの予防と解消の仕方の「人間の理解学」が身につきます。
心の病いの予防と解消の仕方の「人間の理解学」が身につきます。 心の病いに気づける「人間への愛情学」が驚くほど身につきます。
心の病いに気づける「人間への愛情学」が驚くほど身につきます。 「交渉術」の知性と対話の能力が目ざましく進化しつづけます。
「交渉術」の知性と対話の能力が目ざましく進化しつづけます。 相手の心の病理が分かって、正しく改善できるので心から喜ばれます。「心の診断術」
相手の心の病理が分かって、正しく改善できるので心から喜ばれます。「心の診断術」 病気になるということ、病気が治るということが正しく分かる、最高峰の知性が身につきます。
病気になるということ、病気が治るということが正しく分かる、最高峰の知性が身につきます。 朝、起きると無気力。仕事にヤル気が出ません。うつ病でしょうか?
朝、起きると無気力。仕事にヤル気が出ません。うつ病でしょうか?  仕事に行こうとおもうと、緊張して、どうしても行けません。治りますか?
仕事に行こうとおもうと、緊張して、どうしても行けません。治りますか? 


