| 心の病気とは、虚偽の発言が特質です |
平成20年7月19日(土曜日)に、「埼玉県川口・父親刺殺事件」が起こりました。容疑者は、父親の娘です。
中学3年生(15歳)の長女です。
長女は、「なぜ父親を殺害したのか?」の問いに答えて、二つのことを供述しています。
「日頃、勉強しろと言われていた。うざったかった」
「事件の日の夜は、夜12時に寝た。3時に目が覚めた。父親が家族のみんなを殺す夢を見たからだ」。
この長女の供述から、次のような動機の推察がおこなわれています。
「教育による圧迫感は、大人が考えるよりはるかに強い。学校が辛かったのではないか。無断欠席で罪悪感があったはず。発覚時を想像し、精神的に追い込まれたのではないか」(心理カウンセラー。子ども相談室(モモの部屋)主宰・内田良子)
「怖い夢を現実と勘違いしたのではないか。混乱したまま刺してしまった。確定的な殺意などないのではないか。非力な女の子に、父親の肺まで達するような刺し方をする力があるとは思えない。行動抑制が効かない半覚醒状態だったと見るのが自然だ」(睡眠障害に詳しい熊本大、発生医学研究センター粂和彦准教授・くめかずひこ・じゅんきょうじゅ)。
内田良子と粂和彦(くめかずひこ)がここでのべていることは、合理的な因果を納得させるものではありません。万人に該当する普遍性がないということです。「教育による圧迫感」があれば、なぜ、父親を殺すことになるのか?「覚醒(かくせい)障害」があれば、どういうメカニズムで「父親を殺害する」という行動につながるのか?についての筋道立った説明を感じとることはできません。長女の「父親刺殺」の行動に、合理的な動機の説明がないことから、つじつまの合うような意味を後付けしてみせたと思われます。
平成20年8月2日の日経の報道では、長女が最初の供述をひるがえしたと書かれています。
「事件の当日は、12時頃寝たと言ったが、じつは寝ていない。12時からずっと起きていた。寝ないで起きていた」。
「事件の前日(7月18日)、学校からかかってきた電話に出たのは、自分だ。弟ではない。自分が弟になりすませて、姉は風邪で寝ています、と話した」。
報道によれば、県警は、長女の供述を初めから虚偽であると判断していたということです。事件の直後、母親と弟にも事情聴取をしているからです。
弟にも「あなたは、姉の代わりに電話に出ましたか?」と尋ねたでしょう。
当然、弟は県警に嘘を言わなければならない理由はありません。
本当のことを話したでしょう。ここから、長女が虚偽の話をしていると疑われたと思われます。
では、長女は、なぜ「父親を殺害した動機」について虚偽の話をしたのでしょうか。それは、心の病いはもともと、話したり行動すれば「虚偽になる」というようにあらわされるものであるからです。「心の病い」とは、「うつ病」か「分裂病」のことをいいます。「うつ病」にしろ「分裂病」にせよ、その人が自分の「行動」について説明すると、必ず、「虚偽になる」というように言葉で表現されます。「心の病い」とは、必ず「虚偽」の言葉を言いあらわし、「虚偽の言葉」で「行動する」ということを直感的に感じとった発言が次のようなものです。 |
「戦前の教育を復活せよ」
(佐藤愛子、『週刊文春』平成20年8月7日号より、リライト再構成) |
- 新聞に、一連の通り魔事件について、「命の尊さを若者に教えなければいけない」と書いてあった。だが、そんなことを教えられるはずがない。どうすれば教えられるのか、それを教えてほしい。
- なぜ「命の尊さ」を感じない若者が増えているのか?を考えるべきだ。
私は、戦後教育の"負の遺産"だと思う。子どもは、半人前だ。
だから半人前の主体を認めていたら教育はできない。
あるピアノ教師が言っていた。
生徒の親に練習の方法を相談した。すると親は、「子どもに聞いてみます」と言ったという。
このたぐいの話は、いろんなところで聞く。子どもの気持ちを尊重せよ、というのが、戦後教育の根っこにある。みんなガマン知らずに育っている。思いどおりにならない現実にぶつかるとプッツンする若者が出てきたのは、気持ちを尊重する教育の結果だ。
- 昔、子どもにとって親は理不尽きわまるものだった。
学校から帰ってくるとお使いに行けとか赤ん坊のお守りをしろと言う。どんどん用事を言いつける。宿題がある、と言っても、そんなものは後ですればいいと言われる。
言いつける用事のない日は、遊んでばかりいないで、勉強しろ、と言う。
文句を言うと親に口答えするなと言われる。子どもは、しかたなく親の言うことを聞いていた。この理不尽さがじつは、子どもを鍛えた。私は、そう思っている。子どもの頃から理不尽さに馴れていれば、耐性ができる。
だから、プッツンすることもない。
- 日本の若者を変えるには、戦前のような教育、つまり親や教師が子どもを叱り、鍛えて、強い精神力をつけさせるしかない。
- この頃の男性はおとなしい。もう病気かと思うくらいだ。
家庭教育というものは、父親が厳しく子どもを鍛えて、母親が優しく包容するという役割分担があった。今はこれがなくなっている。
優しいお父さんが理想になっている。
- 学校の先生も同じだ。厳しくすれば親が文句を言うという声を耳にする。タガがゆるんでいる。
「暴力はいけない」と何とかのひとつ覚えのように言って育てた結果、「誰でもよかった殺人」が横行するようになった。
- この頃の事件を起こす若者は、不良じゃない。いきなりプッツンする。そしてその罪を親とか社会のせいにする。
- 「秋葉原の無差別殺人」は、「格差社会に要因がある」というような識者の意見があるようだ。
それを信じるなら、私は、容疑者の彼に訊きたい。
「君は、どれだけ努力したの?」。
昔は、自分が認められないと、「今に見ていろ!!」という負けん気が生まれたものだ。それが社会が豊かになりすぎて、人間の本来の競争心が失われている。
|
「死にたい人には重労働を」
(曽野綾子『週刊文春』平成20年8月7日号よりリライト・再構成) |
- 最近の若者の犯罪には、表層的なところから人間の深い部分に至るまで、三つの傾向があると思う。
一つは、小さい頃からトレンディなものに対しての正しい抵抗の姿勢が教えられていない。通り魔が連続しているのは、前の人をマネしているからだ。私の子どもの頃は、人のマネをするのは恥ずかしいことだと教えられた。
二つめは、「誰でもいいから人を殺す」というのは、犯行に及んだ理由がない。人間的じゃないということだ。秋葉原事件の報道を見ると、私は、ショックを感じるというより、文学的にいうと退屈な感じがする。殺人に理由がないからだ。理由があるからこそ人間の行為である。行動に理由がない彼らを私は、人間的に感じられない。
三つめは、他人は、どう感じて生きているのかな?という自覚が足りない。理由なく、いきずりの人に殺されたらどう感じるのか?考えたことがないんでしょうね。
私は、小さい頃にバッタを松葉でいじめた。母親から「虫も痛いわよね、きっと」と教えられた。これで初めて、他者のことを思いやる姿勢ができた。
- 今は、テレビゲームに代表されるバーチャルリアリティの中で育っている。他人のことをおもんぱかる必要がない。
テレビの中の特徴は、実際に血を流さないことだ。他人の痛みが分からない。だから「殺すのは誰でもよかった」と言えるのだ。今の子どもは、情報がたくさん入るから知識はある。しかし、生きている人間との接触があまりにも足りない。
- 子どもの方も、親との距離を考える必要がある。「川口」では親殺しがあり、「八王子」の通り魔も、親を困らせるために犯行に及んだという。
「困らせたいくらいに親が大きな存在なのか?」と嫌味を言ってやりたいくらいだ。それほど親が嫌ならば、家を出ていけばすむ話だ。
- こんな日本を救うには、18歳になったら国民はみんな一年間、合宿で奉仕活動をさせたらいいと私はずっと思っている。合宿では、テレビ、携帯電話は、一切禁止です。農業、漁業、林業などの末端を体験させる。実人生とのつながりを感じさせるのだ。
その奉仕の中で、「人道的な奉仕なんか嫌だ」と思えば、それでいい。
何かを強制され、子どもなりの哲学が形成されることで、耐える力や困難に直面したときの受け流し方を学ぶことは有効だ。
- 「死刑になりたかったから人を殺した」というのは論外だ。そういう人は、みんな集めて重労働をやらせる組織をつくるべきだ。どうせいつか死ぬんなら、せめて、それまでに人様の役に立つようなことをしてもらえばいい。
- メディアにも注文がある。もっと加害者のプライベートな面に立ち入った報道をしてもいいのではないか。
その犯人はどんな家庭に育ったのか?詳細に教えてもらいたい。
でなければ、なぜ事件が起きたのか分かるはずもない。事件を教訓として生かすことなどできないからだ。
|
| 母親と父親による家庭教育の不足が事件をつくり出した |
■佐藤愛子と曽野綾子の「誰でもよかった通り魔事件」についてのコメントをご紹介しました。発言の主旨を整理すると次のとおりです。
「佐藤愛子のコメントの主旨」
- 「誰でもよかった通り魔事件」は、日本の戦後教育の「負の遺産」が背景にある。
- 「戦前の教育」は、親が子どもにガマンを強いていた。おもに父親が叱り、鍛えた。子どもは、ガマンの力が育った。このガマンの力とは、強い精神力のことだ。
- 戦前の「母親」は、父親が子どもに理不尽なガマンを強いると、優しくした。父親と母親の役割りは明確だった。
- 「誰でもいいから人を殺す」というのは、「ガマンの力」の不足からくる「プッツン」だ。子どもの主体(気持ち)を尊重する家庭教育がつくっている。
「曽野綾子のコメントの主旨」
- 家庭教育の中で、「人のマネをすること」は恥ずかしいことだと教えられていない。自分は、「人のマネをするな」と教えられた。「通り魔事件」は、先にやった人のマネをしている事件だ。
- 今の事件は、「犯行に理由がない」ことが特徴だ。理由がないというのは、「人間的じゃない」ということだ。
文学的にいえば、退屈きわまりない。
- 「犯行に理由がない」ということは、「他人はどう思うか?」と他者を思いやる気持ちが不足しているということだ。ケータイ、パソコンなどのゲームによって、「バーチャル感」の中で暮しているせいだ。現実とその接点が無いことが「他人は、どう思うか?」の気持ちの欠如をつくり出している。
- 子どもにも問題がある。親を過大評価している。親に仕返しをするとか、思い知らせてやる、などの発言のことだ。親と自分との間に距離がない。
そんなに親が嫌なら、家を出ていけばすむ話ではないか。
- 対策は「強制によって耐える力、現実と葛藤する力」を育てるしかないのではないか。「18歳になったら、全員、一年間の奉仕活動を強制する」というのが一番である。
■佐藤愛子と曽野綾子がのべていることに共通項があります。「戦前と戦後」、「自分が育った時代の家庭教育と、今の若者が育った家庭教育」の違い、差異の中で、「育て方」によって「誰でもよかった通り魔」のものの考え方がつくられたというものです。
「戦前」もしくは「曽野綾子の育った時代と社会」の中に、「誰でもいいから人を殺す」という事件がなかったのか?と問いかけてみます。思い起こすのは、「母と子の無理心中」や「平成4年12月31日に起きた5人の中学生の女の子が、マンションの7階と8階の間にある踊り場から飛び下りて集団自殺した事件」です。(平成13年8月11日のゼミのケーススタディです)。この事件では、3人の女の子が即死し、2人の女の子が重体になりました。
これらの「事件」は、もちろん「通り魔によって殺害された」というものではありません。しかし、「自分には死ぬ理由も、必然的な動機もないのに、他者の死ぬ意識に巻き込まれた」という「意味」は共通しています。
これらの「事件」は、「なぜ死んだのか?」「なぜ、自分以外の人間を巻き込んだのか?」の理由がハッキリしていると思われています。「無理心中」の場合は、今のこの現実があまりにも辛いので、死んで楽になって、心安らかに過ごそう、といった「思考」が推察されます。
遺書とか書き置きのメモ、生き残った人間の証言などが推察の材料になります。
「誰でもいいから人を殺す」という事件は、「推察の材料」になる「言葉」に共感したり、同情したりして実感できるイメージが思い浮ばないという「事件」の起こり方をしています。動機や理由が分からないと思われている事件です。
しかし、それでも、「無理心中」や「5人の中学生の女の子の集団自殺」と同じように、死ぬべき必然性のある因果関係にもとづいて「死なされる」ということが起きています。本ゼミでは、どんなことにも「原因があるから結果がある」ということを教えてきています。「誰でもいいから人を殺す事件」も、「日本人が美化してきた心中」に原因があるように、やはり原因があります。「無理心中」が「うつ病」なら「誰でもいいから人を殺す事件」も「うつ病」です。「シリアルキラー」といわれる「SM」の性的なイメージの美化の妄想を鮮明化するための殺人は、「分裂病」です。 |
| 「心の病い」の変遷(へんせん)と現在の「心の病い」の特徴 |
「うつ病」の妄想は、ふだんの生活の中で必ずしも「人を殺す妄想のイメージ」は思い浮んでいないという特質をもちます。「分裂病」の妄想は、ふだんの生活、仕事の現実の中で「人を殺す」なり「人の何ごとかを収奪する」というイメージ(妄想)がつねに思い浮んでいます。「うつ病」も「分裂病」も、「対象言語」によって「欲求」が表現されるので、因果の根拠の推察と理解が成り立ちやすいのです。
佐藤愛子と曽野綾子は、心の病気というものが「対象言語」によって言いあらわされていない点を指して、「戦前は」「戦後は」というとらえ方をしています。「私の子どもの頃の家庭教育では」「今の子どもの家庭教育は」というとらえ方です。
佐藤愛子や曽野綾子の「心の病い」のとらえ方は、「心の病い」というものが「対象言語」としてあらわされると、不可解に見えるということがのべられていることになるのです。「心の病い」は、新しいタイプの病気がつくり出されているということではありません。 |
| 「メタ言語」を分かると心の病いのメカニズムが正しく理解できる |
「対象言語」としてあらわされる以前の言葉のことを「メタ言語」といいます。「メタ言語」とは、「脳の働き方のメカニズム」と同じ意味です。「脳の働き方」から見ると、「心の病い」は、一体なぜ、『対象言語』にむすびつかずに、「メタ言語」のまま「行動」にあらわされるようになったのか?が明らかになります。
「心の病気」は、脳の働き方から見るとどのようにあらわされるものでしょうか。
『赤ん坊から見た世界・言語以前の光景』(無藤隆)には、ボールビー、エインズワース、フィールドらによる「愛着」の事例が紹介されていました。
- 「愛着」とは、個人間の親密な人間関係のことである。あたたかい情緒的な絆(きずな)を元にして成立する対人関係である。生涯にわたって親密な人間関係を必要とするが、その始まりが乳児期にある。
- 乳児は、親密で情緒的な関係を形成した対象に対して、それへの接近を維持しようとする。母親の側に居たがる、といったことだ。
- 乳児は、愛着の対象に接近し、その接近を維持することで安心を確保する。その対象を安全基地としてまわりへの探索活動をおこなう。この中で、恐れや不安がもたらされると、また、愛着対象へ接近と接触を求める。
- 乳児は、歩けるようになると、乳児は母親から離れて、まわりを探索するが、しかし、たえず母親の様子をチェックする。定期的に母親のもとへ戻ってはまた、探索におもむく。
- 乳児にとって「愛着」の第一義は母親である。父親、祖父母、年上の兄弟(きょうだい)、保護者も愛着の対象になりうる。
- 乳児は、「愛着」をベースとした探索の中でおもに「感情の喚起」をおこなう。この「感情の喚起」の中では「乳児による認識」が認められる。
1.評価
2.比較やカテゴリー化、推論や判断
3.原因帰属と信念
4.記憶と予期
これらの「認識」は、「甘いものを好む」「苦い味を嫌悪する」「予防注射を苦痛に感じる」「苦痛を感じているのにそれがつづくと怒る、泣く、悲しむ」などの観察をとおして得られた推察である。
|
| 「メタ言語」は「右脳系の脳の働き方」のことである |
■ここで乳児がおこなっていることは、全て脳の働き方のメカニズムによって成り立っていることに注目しましょう。
無藤隆が、乳児の「行動」を観察して、「評価をおこなっている」「比較したり、カテゴリー化をおこなっている」「帰属意識がある」「自分の行動についての信念をもつ」「記憶している」「予期することができる」などと概念化しているのは、すべて「メタ言語」としての表現です。
乳児のこれらの脳の働き方は、五官覚をとおしておこなわれています。五官覚とは、目、耳、手、足、皮ふ、舌、鼻などの「受容器官」のことです。五官覚から受け取った知覚される刺激は、「脊髄」から「脳幹」をとおって、大脳辺縁系に送られます。大脳辺縁系の「視床」によって、「左脳系の海馬」か「右脳系の海馬」にふるい分けられて記憶されます。
しかし、乳児の段階では、「左脳系の海馬」での記憶は、「認知」の次の「認識」によっておこなわれるので、つねに「右脳の働き」が先行しています。
「右脳」は、五官覚の「知覚」とむすびついて、右脳系の大脳辺縁系の中枢神経が「記憶する」のです。
「右脳系」で記憶する「五官覚」のうち「触覚」(認知)をベースにして、「視覚」「聴覚」がそれぞれの独立した知覚を「左脳系の言語野」で認識して「言語化」し、記憶します。乳児の「言葉の生成」と「行動の生成」とは、このような基本メカニズムで成り立っています。
「心の病気」とは、この「言葉の生成と行動の生成」が、「行動を止めてしまう記憶の仕方」に原因があります。
人間が、行動をするには「言葉」が必要です。このことは、どなたにもよくお分りのとおりです。では、「行動が止まる」というときの「言葉」の憶え方とは、一体、どういうものか?が問題になります。 |
| 脳の働き方の基幹システムは「記憶のソースモニタリング」 |
すでに、みなさまには、よくお分りのとおり、「人間の脳の働き方」は、つねに「記憶のソース・モニタリング」を基幹の働き方にしています。人間が、現実のものごとを見る、聞く、そして関わりを成立させようとするとき、脳は、必ず、その対象についての「記憶」があるかどうか?を思い出そうとするのです。これが「記憶のソース・モニタリング」です。
この「思い出すこと」は二通りです。一つは「想起」です。「左脳系の海馬」からエピソードを思い出すことが「想起」です。もう一つは、「表象」(ひょうしょう)です。「右脳系の海馬」からエピソードを思い出してイメージすることが「表象」(ひょうしょう)です。
人間は、「左脳系の海馬」か、「右脳系の海馬」のいずれかから記憶している「エピソード」を思い出し、目の前の対象と一致していれば「行動」を生成する、というように「行動する」のです。
もし、ある人が「右脳系の海馬」のエピソードの記憶を表象させてしか「行動しない」ということがあれば、どうなるでしょうか?「右脳系の海馬」は、「右脳系の大脳辺縁系」の中枢神経に記憶している「行動の内容」をエピソードとして表象します。大脳辺縁系にある中枢神経のおもなものは次のとおりです。
- 線状体…おもに不安の体験を記憶する。
- 扁桃核…「好き」「嫌い」「敵」「味方」の感情的な価値の体験を記憶する。
- 中隔核…目先の快感、利益の体験を記憶する。恐怖の体験も記憶する。この恐怖の体験をイメージして「快感」に変える。
|
| 病気を生成する脳の働き方のメカニズム |
人間は、行動にあたり「言葉」を必要とする、ということは、すでにお話しています。この「右脳系の海馬」に記憶されているエピソードも「言葉」によって表現されます。「行動」には、必ず「言葉」が必要なので、「左脳系の海馬」で記憶されている「言葉」にむすびつけられて表現されるのです。
次のようなケースが該当します。
事例1 「ミャーミャー」(乳児の 発語。猫のこと)
事例2 「おかあちゃん、おみじゅ」(幼児の発語。水が欲しいの意)。
事例3 「マジで?チョーマジならムカツク」
(若者の発語。冗談ではなく、本当の話ならば、不快である、の意)。
事例4 「私、仕事に行ってますけど、ぜんぜん、友人ができないんです」(成人女性の悩みの言葉)
事例5 「あいつ、嫌い!!顔も見たくない」(人間関係で不安を感じやすい人の会話の言葉)
事例6 「働きに行こうとは思うんですが、10年前の面接のときに、たいへん恐い思いをしました。
そのときのことが思い浮んで、働きに行く気が起きないんです」
(働きに行けない人の弁明の言葉)。
事例7 「誰でもいいから人を殺そうと思いました」(秋葉原無差別殺人事件の容疑者の供述)
事例8 「日頃、親から勉強しろと言われていてうざったかった。
夢の中でお父さんが家族を殺す夢を見た」
(埼玉県川口・父親刺殺事件の容疑者、長女の供述)。 |
| 性格とは「キャラクター」と「パーソナリティ」の二つです |
事例の1から8までの言葉は、「左脳系の海馬」で記憶されている言葉です。「右脳系の海馬」に記憶されているエピソードのイメージが「左脳系の海馬」で記憶されている「言葉」にむすびつけられて言いあらわされています。
ポルソナーレは、設立の当初は、このような病理の言葉を「気持ち中心のものの考え方」のことであると定義していました。「気持ち中心」とは、好きだ、嫌いだ、といった感情を価値判断の基準に立てる「ものの考え方」のことです。このような「ものの考え方」をつねにもちつづける人のことを「性格」の特性として、「自然な血スジの気質」を原始的な感情のままにあらわしている、と解析しています。人間の「性格」は、パーソナリティ(社会的なものの考え方を態度、行動、姿勢にあらわすこと)と、もうひとつ「キャラクター」(好き、嫌いの生(なま)の感情をものの考え方にして、態度、行動、姿勢にあらわすこと)との二つで形成されます。事例の1から8までの言葉、態度、行動、姿勢は「キャラクター」(自然な血スジの気質)としての「性格」を身につけている人です。事例を見てお分りのとおり、「キャラクター」とは、「病気のものの考え方」をあらわす人のことをいいます。「右脳系の海馬」の記憶のエピソードのイメージにちょうど適合する「記号としての言葉」を言いあらわすという脳の働き方をメカニズムの特性にしています。
「パーソナリティ」としての性格とはどういうものでしょうか。
佐藤愛子や曽野綾子がいうように、「ガマンの能力がある行動をおこなう」「無媒介に人のマネをしない」「自分の行動を第三者に正しく伝わるように説明する」「自分の行動が、他者にどう見えるか?他者はどう感じるか?などの思いやりの能力をもつ」「現実の中で、辛いことがあっても耐える力をもつ」「不遇な現実にぶつかってもかわしたり、やりすごしたりするなどの葛藤能力をもつ」といった「ものの考え方」のことをいうのでしょう。パーソナリティの定義としてこれだけで充分とはいえませんが、子どもが「4歳」か「5歳」の年齢の時期の、幼児教育の観点から見た「パーソナリティ」としては適切であるといえます。
佐藤愛子と曽野綾子のいう理想的な若者観とは、4歳か、5歳児のレベルの「性格」です。 |
年齢べつの発達段階から見た、
4歳児と5歳児の社会性の発達の到達目標 |
4歳児
- 幼稚園、保育園など中程度の集団の中で、過すことができる。
- 全体がどうなっているか?を理解して、この中で自分のとるべき行動を判断できる。
- 他者のルールある行動に合わせて、集団生活を維持できる。
5歳児
- ものごとの良い、悪いを判断して、よくないことへの批判ができる。
- 相手が困っていることを見たら、サッと助けの手をさしのべることができる。
- 共同生活の中の一員としての役割を分かり、小さな大人としての立居ふるまいの行動ができる。
子どもの「パーソナリティ」はどのように形成されるのでしょうか。ボールビー、エインズワース、フィールドらが観察や実験をとおして確定した「愛着」のシステムにしたがえば、「母親」と「父親」の「愛着の同調」が基盤になります。
「愛着」とは、子どもに情緒的な人間関係の安心の能力を記憶させます。
大人になれば、「不安定な負の状態」に陥っているパートナーにたいして、その「不安定な状態の回復に働きかける」というようにです。パートナーとは、友人、恋人、家族のことです。
「愛着」は、乳児にとっては、「現実のものごとの探索」のベースキャンプでもあると無藤隆はリポートしています。「探索」とは、ものごとと関わりをもつ、ということです。くりかえして反復させる行動は、言葉の「長期記憶の対象」になります。
この「長期記憶」は「愛着」のパートナーの「同期」と「同調」によって記憶が可能になります。これは、本ゼミの前回の号でお話しているとおりです。
子どもの自主的な「行動」は、「同調」によって成り立ちます。「同調」は、「言葉の意味」のメタファーです。
母親の「愛着」の「同調」
- 「共同指示の一環としての喜びの表情」のこと。「言葉の意味」のメタファーになる。
- 乳児・幼児から小学3年生までの子どもの「言葉の学習」のベースになる。
- 小学4年生から中学3年生までは、「同期」はなくなり、「同調」のみとなる。母親の「同調」によって子どもは、「言葉の意味」を記憶しなくても、教科書や仕事の言葉の「丸暗記」が可能になる。つねに「行動停止」の不安定なパーソナリティが身につく。
父親の「愛着」の「同調」
- 父親(男性)の「空間認知」の能力をベースにした想像力の言葉で、子どもの社会の中での体験を追体験するのが「同期」である。子どもの語る体験の実感を、評価するのが父親の「同調」である。
- 父親の「同調」の言葉が無いときが、子どもにとって「パーソナリティ不全」になる。
- 父親の「同調」が無いとは、小学4年から始まって中学3年生までの期間に、距離が無い関係で接した場合のことをいう。
|
| 「愛着」が性格をつくる |
■佐藤愛子は、「日本の父親は子どもに理不尽に厳しく接したが、しかし母親は、優しく暖かくつつみこんだ」とのべています。「母親」の愛着の「同調」はつづいていたということの証言になります。一方、曽野綾子の母親は、「バッタをいじめていると、虫だって痛いと思うよと言った」とのべています。母親は、バッタをいじめる子どもの曽野綾子の孤独さを察してないという「非同調」になるのです。日本の女性は、この二通りのうち、いずれかの母親になった、ということです。佐藤愛子型の女性(母親)が消えて、曽野綾子型の女性(母親)しかいなくなったとき、日本の子どもはパーソナリティを喪失し、「キャラクター中心の性格」を身につけはじめた、ということができましょう。
|

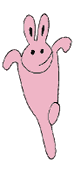


 「女性向け」、「男性の“女性”対応」のカウンセリング・ゼミです。
「女性向け」、「男性の“女性”対応」のカウンセリング・ゼミです。 女性と心を分かち合える「脳」を、最高に発達させる!!が教育の狙いと目的です。女性を「見る」「見たい」、女性から「見られる」「見られたい」関係をつくる、カウンセリング術です。
女性と心を分かち合える「脳」を、最高に発達させる!!が教育の狙いと目的です。女性を「見る」「見たい」、女性から「見られる」「見られたい」関係をつくる、カウンセリング術です。 女性の「脳を健康を働かせる」!安心と安らぎを分かち合う、が教育のテーマと目標です。「気持ちが安心する。だから、知的に考えられる」という女性の本質を支えつづけるカウンセリング術です。
女性の「脳を健康を働かせる」!安心と安らぎを分かち合う、が教育のテーマと目標です。「気持ちが安心する。だから、知的に考えられる」という女性の本質を支えつづけるカウンセリング術です。 女性の脳の働きが伸ばす「人格=パーソナリティ」を目ざましく発達させる!が教育の方針です。
女性が社会性の世界(学校・仕事・社会の規範・人間関係のルール・合理的な思考)と、知的に関われる!を一緒に考えつづけるカウンセリング術です。
女性の脳の働きが伸ばす「人格=パーソナリティ」を目ざましく発達させる!が教育の方針です。
女性が社会性の世界(学校・仕事・社会の規範・人間関係のルール・合理的な思考)と、知的に関われる!を一緒に考えつづけるカウンセリング術です。 ストレスを楽々のりこえる女性の「脳」を育てる!!が教育の人気の秘密です。女性は、脳の働きと五官覚の働き(察知して安心。共生して気持ちよくなる)とぴったりむすびついて、一生、発達しつづけます。
ストレスを楽々のりこえる女性の「脳」を育てる!!が教育の人気の秘密です。女性は、脳の働きと五官覚の働き(察知して安心。共生して気持ちよくなる)とぴったりむすびついて、一生、発達しつづけます。  人の性格(ものの考え方)が手に取るように分かる「心の観察学」
人の性格(ものの考え方)が手に取るように分かる「心の観察学」 心の病いに感染させられない「人間の関係学」がステキに身につきます。
心の病いに感染させられない「人間の関係学」がステキに身につきます。 心の病いを救出する、心と心をつなぐ「夢の架け橋術」
心の病いを救出する、心と心をつなぐ「夢の架け橋術」 相手に好かれる「対話術」がまぶしく輝くので、毎日が心の旅路。
相手に好かれる「対話術」がまぶしく輝くので、毎日が心の旅路。 相手の心の働きのつまづきが正しく分かって、「正しい心の地図をつくれる」ので、損失、リスクを防げます。
相手の心の働きのつまづきが正しく分かって、「正しい心の地図をつくれる」ので、損失、リスクを防げます。 学校に行くとイジメがこわいんです。私にも原因ありますか?
学校に行くとイジメがこわいんです。私にも原因ありますか?  怒りっぽいんです。反省しても、くりかえしています。治りますか?
怒りっぽいんです。反省しても、くりかえしています。治りますか?  「仕事・人生・組織に活かすカウンセリング」です。他者の心身のトラブルを解消できれば、自然に自分の心身のトラブルも解消します。
「仕事・人生・組織に活かすカウンセリング」です。他者の心身のトラブルを解消できれば、自然に自分の心身のトラブルも解消します。 プロ「教育者」向けのカウンセリング・ゼミです。
プロ「教育者」向けのカウンセリング・ゼミです。 「脳の健康を向上させる」、が教育のテーマと目標です。「指示性のカウンセリング」は、「考えたことを実行し、考えないことは実行しない」
という人間の本質を、最後まで励まし、勇気づけるカウンセリング術です。
「脳の健康を向上させる」、が教育のテーマと目標です。「指示性のカウンセリング」は、「考えたことを実行し、考えないことは実行しない」
という人間の本質を、最後まで励まし、勇気づけるカウンセリング術です。 脳の働きがつくる「人格=パーソナリティ」を育てる!が教育の方針です。
脳の働きがつくる「人格=パーソナリティ」を育てる!が教育の方針です。 ストレスに強い、元気に働く「脳」に成長させる!!が教育の魅力です。
ストレスに強い、元気に働く「脳」に成長させる!!が教育の魅力です。 「心の病いの診断学」が楽しく身につきます。
「心の病いの診断学」が楽しく身につきます。 心の病いの予防と解消の仕方の「人間の理解学」が身につきます。
心の病いの予防と解消の仕方の「人間の理解学」が身につきます。 心の病いに気づける「人間への愛情学」が驚くほど身につきます。
心の病いに気づける「人間への愛情学」が驚くほど身につきます。 「交渉術」の知性と対話の能力が目ざましく進化しつづけます。
「交渉術」の知性と対話の能力が目ざましく進化しつづけます。 相手の心の病理が分かって、正しく改善できるので心から喜ばれます。「心の診断術」
相手の心の病理が分かって、正しく改善できるので心から喜ばれます。「心の診断術」 病気になるということ、病気が治るということが正しく分かる、最高峰の知性が身につきます。
病気になるということ、病気が治るということが正しく分かる、最高峰の知性が身につきます。 朝、起きると無気力。仕事にヤル気が出ません。うつ病でしょうか?
朝、起きると無気力。仕事にヤル気が出ません。うつ病でしょうか?  仕事に行こうとおもうと、緊張して、どうしても行けません。治りますか?
仕事に行こうとおもうと、緊張して、どうしても行けません。治りますか? 


